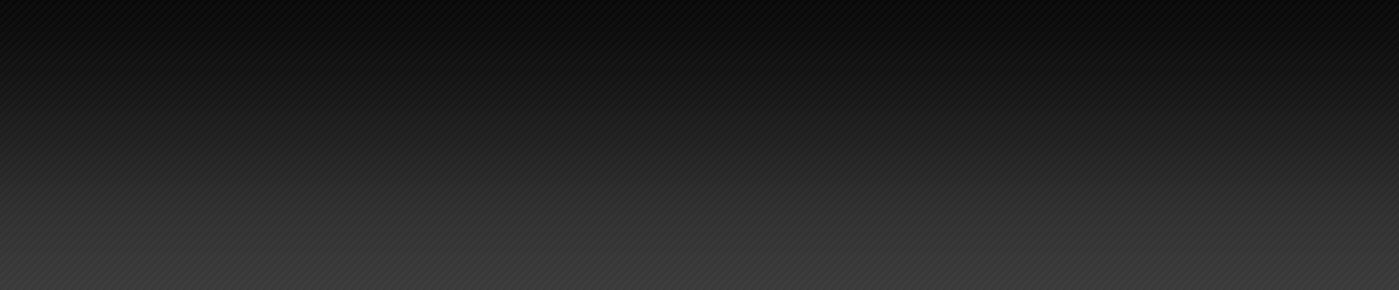

2022年6月に発足したEUNIC関西設立を記念して、EUNIC関西と京都芸術センターは、ハイブリッド型シンポジウム「AIR on air 2.0」を開催しました。
コロナ下の2020年12月にオンラインで開催したシンポジウム「AIR on air」からの議論を引き継ぎ、目まぐるしくシフトする社会情勢下でのアーティスト・イン・レジデンス(AIR)の現在地を確認し、どのような変革が求められているのかを議論した本シンポジウムについて、前回のシンポジウムでは総合ファシリテーターを務めた石井潤一郎さんにレポートしていただきました。
「性急さを必要としたパンデミックへの対応は、部分的には終息へと向かい始めています。しかしこの危機は戦争や緊張、そして地球温暖化などの他の問題が、ますます深刻なものであるということをわたしたちに知らしめました。わたしたちは今、この地球の上で『どのように生きてゆけるのか』そして『どのように生きてゆきたいのか』といった、大きな問題と向かい合わなければなりません」
2022年12月16日、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、ヴィラ九条山、アンスティチュ・フランセ関西、オランダ王国大使館、京都芸術センターによって組織されたハイブリッド・シンポジウム「AIR on air 2.0」の開幕にあたり、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、館長のエンツィオ・ヴェッツェルはそう述べた。
芸術的創作のためのスペース、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)はどのようにアーティストの活動を支援できるのだろうか。芸術的な自由を維持することがその役割なのだろうか。あるいはわたしたちが直面する地球規模の、そして新しい要求に対して自由を開放してゆくことがその使命なのだろうか。
二年前、2020年12月、コロナ禍で移動の自由が著しく制限される中、オンラインで開催された第一回目の同シンポジウムでは「移動の自由」「脱炭素化(グリーン・モービリティ)」そして「デジタル化」といった観点から、AIRの展望が議論された。第二回目となる今回は、特に「アート制作における気候変動の危機」と「連帯とケア」というふたつの問題に焦点を絞って、各分野の専門家を招きハイブリッド形式で意見交換が行われた。
ポスト・パンデミックとも呼ばれ始めているこの時代、AIRにはどのような機能が求められているのか。開会の挨拶でアンスティチュ・フランセ・パリ本部のエヴァ・ニェン=ビン理事長からは「例えばフランスのAIRでは、2020年のベイルート港爆発事故以降、100名を超えるレバノンのアーティストを受け入れてきました。2022年、ロシアのウクライナ侵攻の後にも、多くのウクライナ・アーティストを受け入れています。このような危機的な状況の中で、AIRはどのようにアーティストたちを迎え入れることができるのでしょうか。また同国で危機が続いている中、AIRの『滞在期間終了』を、どのように考えることができるのでしょうか。ぜひ、今回のひとつの議題にしていただきたいと思います」との言葉も寄せられた。

Photo: AIR on air 2.0
シンポジウムの第一部では「アート制作における気候変動の危機」に関連して、四人の登壇者によるプレゼンテーションが行われた。
森美術館アジャンクト・キュレーターのマーティン・ゲルマンは、国際芸術祭「あいち2022」で紹介されていた作家、ローター・バウムガルテン(1944-2018)と、森美術館の「MAMスクリーン017」で、パートナーであるロバート・スミッソン(1938-1973)との共作が上映されている作家、ナンシー・ホルト(1938-2014)を取り上げた。
バウムガルテンは60年代後半から70年代初頭にかけて、特に生態学の観点から、西洋の言説や近代社会を牽引する思考のシステムを離れ、代わりにアマゾンの熱帯雨林に暮らすヤノマミ族の、循環型の生活にその源泉を求めたアーティストである。
一方、さまざまな制作を行ってきたナンシー・ホルトは、80年代、わたしたちの身の回りにある「インフラ」に注目し始めた。「インフラ」は確実にわたしたちの周囲にある。にも関わらず、通常は目に見えない。ホルトは物質に何かを加えて作品を「制作」をするのではなく、すでにある(が見えなくなっている)ものを「見えるようにする」というアプローチで作品の制作を行なっていたのである。
ゲルマンはわたしたちが今日直面する問題は、昨今突如として起こり始めたものではなく、60年代や70年代、80年代にも確実に存在していた問題であり、当時のアーティストたちの取り組みを通して、今日のわたしたちが考えるべきことが見えてくるのではないか、と指摘する。
◉
二人目のプレゼンテーター、オランダ、ヤン・ファン・エイク・アカデミーのジュリア・ベリネッティは、同インスティテューションが2020年から、ロンドン芸術大学(UAL)セントラル・セント・マーチンズの大学院「マテリアル・フューチャーズ」および「グリーン・アート・ラボ・アライアンス(GALA)」と共同で開発している「フーチャー・マテリアル・バンク」を紹介した。
同プログラムは、持続可能な芸術的実践を促進し、支援するために開発されたオンラインの「素材アーカイヴ」である。「バンク」には2022年2月現在、地球上のさまざまな地域のアーティスト、デザイナー、そしてその他の実践者たちから寄せられた、300を超える非毒性で持続可能な素材情報が収蔵されている。
「わたしたちは、これらを『フューチャー・マテリアル(未来素材)』と呼んでいますが、必ずしも『新しい素材』である必要はありません。これは『未来に通用する素材』であるという意味なのです。わたしたちは『未来』の概念についても議論しています」
ベリネッティは語る。「フューチャー・マテリアル・バンク」は、伝統的な工芸品やその技術を再利用したり再発見したりすることで、人間と環境の間で、よりバランスのとれた芸術的実践を復活させる、あるいは制作に関わる者に、そうしたインスピレーションを与えることを目的としている。
◉
三人目のプレゼンテーターとなる三原聡一郎は、テクノロジーを使用して自然の循環をテーマに作品制作を行なうアーティストである。三原は自身の創作から、特に「環境破壊」や「気候変動」に関連した三作品を紹介した。
2011年の東日本大震災をきっかけに制作されたサウンド・インスタレーション《鈴 / bell》(2013)は、放射線センサーによって展示空間内の線量を計測し、その数値によって風鈴を鳴らす。
空気循環のないドームの中で鈴が鳴る様は一見すると奇妙な現象である。「鈴」は東日本の伝統において、人の世と人外の世の境界にあり、外から来る邪悪なものを知らせるという役割を負った。三原は同作を通して「放射線」という人間に知覚できないものを、計測器や数値情報だけではなく、文化的な体験として視覚化しようと試みた。
三原はまた《無主物 / Res Nullius》(2020)と題した作品によって、わたしたちが日々非意識的に触れている「水」を主題として取り上げた。世界的な気候変動でますます頻繁に報告される水害や渇水、そもそも「水」とはどこにあるのだろうか。
水蒸気を含んだ空気が冷やされて凝縮すると、物質の表面に「結露」として水分が生じる。三原はこの現象を利用して、冷却デバイスを配置した展示空間の空気中から水分を生じさせ、また作品空間には「川」や「雨」のような演出を施し、わたしたちが普段気に留めることの少ない「水の循環」を描き出したのである。
自然現象とメディア・テクノロジーを融合させたような取り組みを行う三原は最後に、東日本大震災以降、自身で取り組んできたコンポスト・プロジェクトを紹介した。三原自身が「空気(酸素)を使う微生物との対話」とも形容するこの《土をつくる / making soil》(2021)プロジェクトは、現在進行形でバケツを回転させ、空気を攪拌させている状態をオンラインでライブ公開している。
◉
第一部最後のプレゼンテーターは、フランクフルトでハッセルホフというスペースを運営しているフェリックス・グローセ=ローマンである。グローセ=ローマンはアーティストたちが使い古しの素材を使って仕事をしているのを見て「マテリアル・フュア・アレ」という中古素材倉庫の設立を考えるようになった。
展覧会では多くの資材が使用される。そしてその中には高価で貴重な材料もある。一度使われただけのこれらの材料が捨てられてしまうなどということは考えられない。一度使用された材料を保存し、アーティストやアート・プロデューサーたちが新しい展覧会に再利用できるように管理する。グローセ=ローマンの取り組みは資源の再利用を促す。
中古素材を管理するにあたって、必要なことはふたつある。素材を保存しておける広い場所と、保存している素材を管理する方法である。「マテリアル・フュア・アレ」ではダルムシュタット工科大学と共同でデジタルアプリを開発し、素材をデジタル化して手に取りやすくするとともに、これらの素材をデジタルデザイン工程で使用できるようにした。
「わたしたちが本当にやろうとしていることは、劇場、美術館、舞台、アート・フェアなど、組織化されたプロダクションの過程において、これらの中古素材が利用されるようにすることです」
2022年カッセルで行われたドクメンタ15では、芸術における再利用性についての問題を提起するために、古い舞台美術の一部を使用した部屋を設置した。室内に再制作された犬の頭には200平方メートルの毛皮と、金属製の構造物が内部に使用されている。
ロシアの軍事行動やパンデミックの後遺症から、資源不足がますます顕在化した今日、この「再利用」という活動はますます重要なものとなってきている。「マテリアル・フュア・アレ(訳:すべての人のための素材)」は、組織化された素材の循環という議論を深めようとしているのである。
◉
前半のプレゼンテーションを終えて、NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT / エイト]のプログラム・ディレクターで、第一部のモデレーターを務めるロジャー・マクドナルドからは、気候変動という(もはや「気候危機」と呼んでもよいかもしれない)問題に関して、同じ地球上に住むわたしたちではあるが、生活している国や地域、どういったメディアから情報を得ているか、またどういった社会制度や政治制度の元に生活しているかによって、日常生活レベルでの意識の持ち方が大きく異なってくるのではないか、という指摘の声があがった。
わたしたちは、今日こうして直面する地球規模の問題に対して、どのような思考と態度を取ることができるのだろうか。今回のようなシンポジウム、特に横への広がりが強いグローバルな「AIR」というネットワークを通して、わたしたちは世界の各地で行われている取り組みを知ることができる。遠く離れた場所からの声に耳を傾け、そして共に考えることによって、わたしたちの「時代の感覚」は維持され(あるいはそこでこそ培われ)それぞれの地域で、それぞれに特化した活動に還元してゆくことができるのではないだろうか。

Photo: AIR on air 2.0
プレゼンテーションは後半、第二部へと移行し「連帯とケア」というテーマに関連して、さらに四人の登壇者がプレゼンテーションを行った。
ウクライナのアートセンターIZOLYATSIA、ディベロップメント・ディレクター、ミハイロ・グルボキは同スペースの現在を報告した。
IZOLYATSIAは2010年にウクライナ東部の都市ドネツクで、古い工業施設を再利用した施設として設立された。教育、芸術、そしてアーティスト・イン・レジデンス・プログラムを備えた複合文化施設として広く一般に開放されていた同施設は、しかし2014年、ロシアのクリミア侵攻によりドネツクが制圧されるとロシア軍によって占拠され、その文化施設としての機能は失われた。現在ここは軍事施設のひとつとなり、拷問さえ行われる収容所として使用されている。
IZOLYATSIAは2014年、キーウに古い造船所を再利用した同様の施設を立ち上げる。しかしここも2022年のロシア侵攻により活動の一部は破壊され、再び閉鎖を余儀なくされた。場所を失ったIZOLYATSIAは現在、オンラインをベースにした活動に専念している。
オンラインでの主な活動とは、欧州連合からの資金支援を受けながら、ウクライナで文化活動を続けるアーティストやインスティテューションを支援するものである。「支援」の種類は多岐にわたる。AIRは爆撃で住む場所を失くしたアーティストの助けになるし、危険な地域から避難する安全な行き先ともなりえる。ウクライナの比較的安全な地域へと避難したアーティストに対しては、その地域の文化団体に打ち解けることができるようにする支援も必要であるし、他国が運営するレジデンスや文化支援プログラムの情報が、個々のアーティストにまで行き届かない場合も多い。このような情報の提供や共有もアーティストを助ける重要な支援である。
グルボキはベルリンとパリで行われたウクライナ・アーティストの展覧会を紹介しながら、トークを次のように締めくくった。
「ウクライナの現在の声を海外に伝えるという意味で、ウクライナのアーティストの仕事は非常に重要です。つまりこれは文化外交のフレームにも入るのです。残念ながらこのような時勢にあって、多くのウクライナ・アーティストは単に自分自身の作品やプロジェクトのためにやって来るわけではありません。国を代表しているのです。彼らはウクライナで何が起きているのかについて語ります。彼らはウクライナで、人々が何を経験しているのかを伝えるのです」

“Where is the time project” 2012, Donetsk, IZOLYATSIA
Photo by Ruslan Semichov
◉
オランダを拠点とし、世界最大級のAIRデータベースを誇る、ダッチカルチャー|トランス・アーティスツのコーディネーター、自身でもアーティストであるハイジ・ヴォーゲルは豊富な経験から彼女自身の見解を述べた。
同団体ではロシアの軍事侵攻の直後に、ウクライナから避難してきたアーティストをスペインのAIRに紹介した。これがうまく運んだことから、トランス・アーティスツはキーウのパートナーであるハウス・オブ・ヨーロッパと提携して、ウクライナ・アーティストとオランダのAIRを結びつける活動を始めた。
「これは非常に自然な流れでした。そして多くの人々がこの行動に共感してくれました。したがってわたしたちはそれが何を意味するのか、つまりアーティストにとってレジデンスとはなにか、レジデンスのモデルを見直し、ホスピタリティという考え方、特にこの危機的な状況において今後『レジデンス』という考え方を、どう発展させてゆけば良いのかと考えるきっかけとなりました¹」
ヴォーゲルはまた、こうした支援のネットワークが、いかに迅速に動くことができるかに驚いたという。これまで長い時間をかけて確立し、そして維持してきた文化的な協力体制やネットワークが、危機に直面するわたしたちを助けてくれている。わたしたちは今ドアを開き、戦火を逃れてきた人々が「安全だ」と感じられる場所をつくることが必要なのだ、とヴォーゲルは語る。
◉
「1965年の開館以来、戦後から今日に至るまで、シテ・アンテルナショナル・デ・ザールは亡命した芸術家を迎え入れ支援する、芸術家にとって常に『安全な場所』であることを目指してきました」
パリのシテ・アンテルナショナル・デ・ザールからは、レジデンス部門長、ヴィンセント・ゴンザレスがプレゼンテーションに参加した。
1950年代に建築家フェリックス・ブルノーによって構想され、1965年に開館した同施設は(時代を想像してもわかる通り)第二次世界大戦の影響を強く受けている。「シテ・アンテルナショナル・デ・ザール(国際芸術都市)」という構想そのものが、積極的な平和への意志に基づいている。
325のスタジオを備え、90カ国から年間1,000人を越すアーティストを受け入れている同施設は、アーティスト・イン・レジデンスのスタジオというよりも「コミュニティ」、あらゆる分野、あらゆる世代、あらゆる国籍のアーティストがパリに来て、尊厳のある生活を送りながら仕事をすることができる「都市」のようなものである、とゴンザレスは語る。世界的にもかなり早い段階から国際的な活動を行ってきたシテ・デ・ザールは1965年、ポーランドから「避難民」という立場でフランスに入国してきたピアニストを、UN(国際連合)からの合意を得た上で「アーティスト」として滞在させた。以来、シテでは多くの亡命者や避難民アーティストを受け入れてきた。2011年からはパリ市と提携し「ICORN(International Cities Of Refuge Network)/ 避難民ネットワークの国際都市」の公式機関として、アフガニスタン、イエメン、バングラデシュからのアーティストには、二年間という長期の滞在を可能にしている。
現在シテには、ウクライナやミャンマーからのアーティストも多く滞在している。シテ・アンテルナショナル・デ・ザールは1965年の開館当時より、常に紛争地域の延長線上にあり、緊急事態の延長線上にあり、したがって今日の世界情勢の縮図の様相を描きながら、常に、支援の必要なアーティストたちに「安全だと感じられる場所」を提供し続けているのである。
◉
第二部最後の登壇者は、2010年に設立され、京都を舞台に国内外の先進的で実験的なアーティストの取り組みを紹介する、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭の共同ディレクター、ジュリエット・ナップとなった。
KYOTO EXPERIMENTでは毎年、国内外の先進的なアーティストを迎え、演劇やダンスのみならず、美術、デザイン、建築などのジャンルを越境した実験的な舞台作品を紹介している。この取り組みの中では毎年3-5の新作が制作されており、つまりアーティストに「滞在制作」の機会を提供しているという点において、KYOTO EXPERIMENTは「レジデンス」に近しい機能も果たしているのである。
2020年、10年目を迎えた芸術祭は新体制へと移行した。これまでの「Shows(上演プログラム)」に加え、アーティストが中心となり京都、関西の地域文化をリサーチする「Kansai Studies(関西スタディーズ)」、フェスティバルを構成するにあたり、その背景にあるさまざまな事象に対する理解をトークやワークショップを通して深める「Super Knowledge for the Future( スーパー・ナレッジ・フォー・ザ・フューチャー [SKF]」も新設された。ジュリエット・ナップは語る。
「『上演プログラム』は、今の日本で見られることが重要だと思われる、先鋭的で実験的なアーティストの作品をラインナップしています。今年はタイとイランのアーティストも紹介しました。この2つの国では、現在激しい抗議デモが起こっており、政治的な激動の時期にあります。フェスティバルにとって、現地の文脈に対してラディカルな姿勢を取るこれらのアーティストを紹介するのは、とても重要なことです。また彼らの作品を紹介するということは、彼らの語る文脈を観客に正しく紹介するということでもあります。わたしたちは『SKF』で、政治と芸術を巡るシリーズのトークを開催し、沖縄での政治問題、タイでのアーティストたちの取り組み、そしてロシアでのアーティストたちの取り組みを見てきました」
◉
後半、第二部のプレゼンテーションを終えて、モデレーターを務めた京都芸術センター、アーツ・アドバイザー、京都市文化政策コーディネーターの山本麻友美は、ウクライナのようにまさに今支援を必要としている「緊急性」を重要とした上で、AIRの定める滞在期間を終えた後の「アフター・レジデンス」をどうしてゆくのか、そして国際的な支援のネットワークが広がってゆく中で、実際に戦争のような危機的な状況から避難してきたアーティストたちには、どのような支援が可能なのか、という問いを投げかけた。
トランザーティスツのヴォーゲルは、戦災などの状況を語るにあたり、レジデンスは国境を超えた同僚に対する最初の反応のひとつとなり得るし、文化的な領域で活動する人々がいかにお互いにとって意味のあるつながりを広げ、支援の輪を増幅することができるのかという、大きな可能性を持っているとした上で、しかしやはりAIRは、継続的なサポートや支援のための最終的な解決策とはなり得ない、との見解を述べた。

以下、ハイジ・ヴォーゲルの言葉の要約をもって、この記事の締めくくりとしたい。
「AIRは、現在危機的な状況にある国の政府体制が持ち直し、一時的にでも、アーティストたちに社会の中での居場所を見つけ、必要な支援を提供できるようになるまでの最初の解決策としてはとても良い方法だと思います。しかしながら、わたしたち(AIR)が取り組んでいること以上に、できることも多くあると思うのです。例えばブリュッセルには市の協力による施設で、音楽を奏で、絵画を描き、料理をできるスペースがあります。また小さな団体ですが、文化的な技能を持ったニューカマーたち(言葉の問題も重要です。彼らは「難民」ではなく「ニューカマー」と呼ぶのです)に、文化的なコネクションを見つける手伝いを行うチームが組織されています。
わたしたち自身にも、学ばなければならないことが多くあります。例えば政治は『難民の流入』や『人の洪水』『国が溢れ返る』といった表現を好んで使います。わたしたちはこのような言葉に対して、もっと批判的にならなければいけないと思います。『問題』をどのように呼称するのか、『政治的な失敗』や『政策の失敗』と呼ぶこともできるでしょう。そうすると見方が完全に逆転します。関係性もまるで変わってきます。わたしは先ほどジュリエット・ナップが言ったことは非常に重要であると思います。アーティストがプレゼンテーションを行う際には、観客を教育することも重要なのです。観客とともに文脈を学んでゆくこと。これはレジデンスのような文化機関を運営する、わたしたちの使命でもあります。どのようにお互いの文脈を理解してゆくのか、なにが重要でそうでないのか、それを理解することは、どのように投資し、どのように協働してゆくのかを考えることでもあるのです」
¹ トランス・アーティスツはKunstenpunt(ブリュッセル)とともに、この議論を深めるため文化や人文学の専門家を招きピア・ツー・ピアのミーティング「Future Hospitalities」を実施している。
https://www.transartists.org/en/news/future-hospitalities-hosting-learning-and-changing
石井潤一郎(いしい じゅんいちろう)/ICA京都レジデンシーズ・コーディネーター
1975年、福岡生まれ。美術作家。2004年よりアジアから中東、ヨーロッパの「アートの周縁 / インターローカルな場」を巡りながら20カ国以上で作品を制作・発表。国際展『10th ISTANBUL BIENNIAL : Nightcomers(トルコ 2007)』『4th / 5th TashkentAle(ウズベキスタン 2008 / 2010)』『2nd Moscow Biennale for Young Art(ロシア 2010)』『ARTISTERIUM IV / VI(グルジア 2011 / 2013)』『2nd / 3rd Larnaca Biennale(キプロス 2021 / 2023)』参加他、個展、グループ展多数。2020年よりICA KyotoでAIRのネットワーク作りを行う一方、KIKA gallery(京都)で展覧会作りにも関わっている。京都精華大学非常勤講師。
https://junichiroishii.com/
ハイブリッド・シンポジウム「AIR on air 2.0」
日時:2022年12月16日 (金)
会場:ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川/オンラインアート制作における気候変動の危機-ヨーロッパと日本の視点から考える
三原聡一郎(アーティスト/日本)
ジュリア・ベリネッティ(ヤン・ファン・エイク・アカデミー/オランダ)
マーティン・ゲルマン(森美術館アジャンクト・キュレーター、ドイツ/日本)
フェリックス・グローセ=ローマン(マテリアル・ファー・アーレ&ハッセルホフ ディレクター/ドイツ)
モデレーター:ロジャー・マクドナルド(NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT]プログラムディレクター/日本)連帯とケア
ハイジ・ヴォーゲル (ダッチカルチャー|トランザーティスツ コーディネーター、アーティスト/オランダ)
ジュリエット・ナップ(KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭共同ディレクター/日本)
ミハイロ・グルボキ(イゾラツィア・アート・センター ディベロップメントディレクター/ウクライナ)
ヴィンセント・ゴンザレス(シテ・アンテルナショナル・デ・ザール レジデンス部門長/フランス)
モデレーター:山本麻友美(京都芸術センターアーツアドバイザー、京都市文化政策コーディネーター /日本)主催:EUNIC関西(ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、 ヴィラ九条山、アンスティチュ・フランセ関西、オランダ王国大使館)、京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)
協力:AIR_J、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、在大阪オランダ王国総領事館
企画協力:小田井真美(さっぽろ天神山アートスタジオ)、東海林慎太郎(NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT])EUNIC – European Union National Institutes for Culture – は、欧州文化機関連合ネットワークです。EUNIC関西クラスターは、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、ヴィラ九条山、アンスティチュ・フランセ関西、在日オランダ王国大使館のイニシアティブにより、2022年6月に設立されました。EUNIC関西は、EUと日本の関西地域の文化の架け橋となることを目的とし、ヨーロッパと関西の文化・芸術セクターのコネクティビティ(繋がり・接続性)と、ヨーロッパと日本のアーティストのモビリティに貢献します。
▶AIR on air オンラインシンポジウム – パンデミック下におけるアーティスト・イン・レジデンス レポート
2024.8.5ヨーロッパでのアーティスト・イン・レジデンスの舵取りの仕方
2024.7.19アーカイブ:AIR@EU開設記念 オンライン連続講座「ヨーロッパでのアーティストの滞在制作・仕事・生活」
2024.6.12Acasă la Hundorf 滞在記 アーティスト:三宅珠子
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕