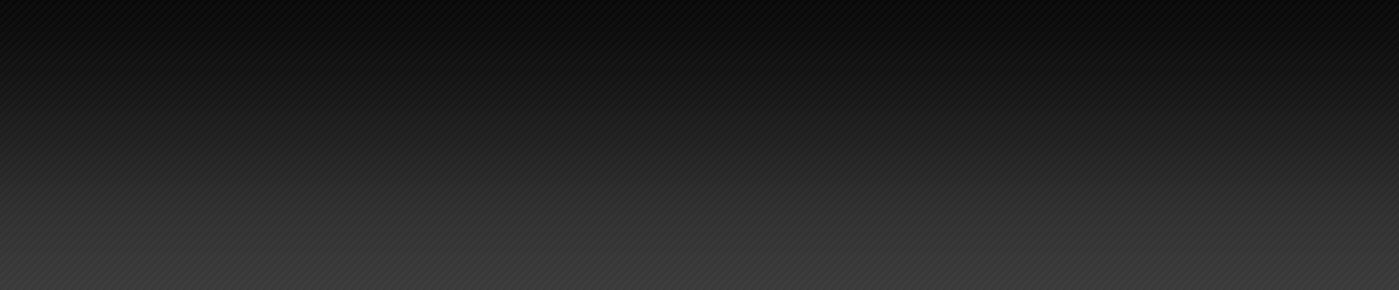


北澤潤《LOST TERMINAL》
“ウソから出た、まこと -地域を超えていま生まれ出るアート” 展示風景
(十和田市現代美術館、青森、2019年)撮影:小山田邦哉
新型コロナウイルスが、いまだに世界中で猛威をふるっている。その病原体は、芸術・文化を含むあらゆる分野に影響を及ぼした。本稿は、新型コロナウイルスが「ソーシャリー・エンゲージド・アート」に与えた影響に焦点をしぼって考察する。後述のように、日本におけるソーシャリー・エンゲージド・アートの隆盛と発展には、アーティスト・イン・レジデンスが重要な役割を果たした。本稿では、今後ソーシャリー・エンゲージド・アートがどのように変わっていくかについても、(あくまで予測の範疇ではあるが)自分なりの見解を示したい。ソーシャリー・エンゲージド・アートと密接なつながりのあるアーティスト・イン・レジデンスは、ソーシャリー・エンゲージド・アートの変化にともなって、いかなる変容を遂げるのか——あるいは、遂げるべきであろうか。
「ソーシャリー・エンゲージド・アート(Socially Engaged Art, SEA)」は公共領域との交わりを志向し、社会・政治的な問題に独自の仕方で取り組むことを目指す現代美術の社会的実践を指す言葉である。日本語では「社会と関わる芸術」や「社会関与型アート」と訳されることもあるが、カタカナのままの名称も普及している。この用語は2000年以降の欧米で広く使用されるようになったが、公共圏と関わろうとする芸術実践は2000年代に入るずっと以前から存在していた。重要なことは、「社会と関わる芸術」を意味する用語が、近年になって美術批評・美術理論の領域で頻繁に議論されるようになったという事実である。おそらく、その背後にはアートがポジティブな社会変革の道具となりうることを希求する、批評家や理論家たちの——さらに一般化すれば、社会全体の——期待が見え隠れする。
ソーシャリー・エンゲージド・アート概念の波は、日本にも届いた。日本の現代美術シーンでも、特に3.11を経験した2010年代の初め以来、この言葉が盛んに援用されている。ただし、日本のソーシャリー・エンゲージド・アートにまつわる理論と実践には、欧米とは異なる(もちろん「欧米」も一枚岩ではないが)特殊な事情があることに注意をうながしたい。その事情とは、しばしば「アート・プロジェクト」という言葉が「ソーシャリー・エンゲージド・アート」と互換的に使用されるというものである。一般に、この用語は中長期的なスパンで計画・実施され、人々との交わりのなかで発展していくプロジェクト型の芸術実践を指す。こうした芸術実践は東京や大阪などの都市部だけではなく、過疎地域を含む日本全土の様々な地域で展開されてきた。
こうした現象の背景には、2000年代以降に日本各地で急増した地方芸術祭(ビエンナーレ、トリエンナーレなど)の存在がある。とりわけ日本で活動する若手〜中堅のアーティストたちにとって、こうした地方芸術祭は美術制作を通して地域の問題にアプローチしたり、幅広い年齢層の地域住民とのインタラクションのなかでアート作品を作り上げたりするための貴重な機会を提供してきた。
芸術と社会が交差する地点としてのアート・プロジェクトが日本で開花したもうひとつの背景として、同じく2000年代以降に日本で増加したアーティスト・イン・レジデンスの存在を見逃すことはできない。2000年代に突入してから日本で続々と開始された実験的なアーティスト・イン・レジデンスのプログラムは、海外のアーティストたちに加えて、国内のアーティストたちを数多く招聘してきた。そのなかにはすでにエスタブリッシュされた著名アーティストもいれば、これからアート・シーンで台頭していこうとする野心的な若手アーティストもいた。日本各地の大小様々なアーティスト・イン・レジデンスは、芸術祭と同様、国内のソーシャリー・エンゲージド・アーティストたちに貴重な制作と発表の場を用意してきた。
しばしばローカルな文脈のなかで展開されるアート・プロジェクトは、日本ではときに「地域アート」という呼称の下に論じられる。この用語には、もともとは批判的含意が込められていたことに留意したい。この用語を最初に提示したSF批評家の藤田直哉は、2014年に「前衛のゾンビたち」と題された論考を雑誌『すばる』にて発表した。その副題は「地域アートの諸問題」であった。藤田の論考は、アート・プロジェクトとして各地で展開される芸術実践の問題を——その一定の意義や効果を認めつつも——批判的に検証するものであった。要約すれば、昨今のアート・プロジェクトではアートが前衛的な社会変革の力を喪失し、地域振興の道具になっていることを彼は懸念していた。
それに対して、アーティスト・イン・レジデンスなどの現場で実際にアート・プロジェクトに関与する人々からは、多様なアート・プロジェクト実践を「地域アート」というアンブレラ・ターム(包括的総称)で十把一絡げに論じてしまうことへの疑義も提出されている。彼・彼女らは、藤田の批判が適切である事例もたしかに存在することを認めつつも、単なる「地域振興の道具」ではないアート・プロジェクトの実例を紹介することで、それぞれのプロジェクトを個別具体的かつ丁寧に検証する必要性を提唱している。2020年に出版された『地域アートはどこにある?』(十和田市現代美術館編、堀之内出版)は、そうした検証の具体例となる重要な参考文献のひとつである。
個人的な話になるが、筆者自身も作家として活動しており、日本のアーティスト・イン・レジデンスを実際に体験している。2015年、まだロンドン芸術大学で博士課程を行なっていたころ、京都芸術センターのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムに参加した。2ヶ月ほど京都に滞在して制作を行い、その成果発表として個展を開催した。そのときに筆者が提案したアート・プロジェクトは、主に京都市に住む多様な文化的・民族的・世代的バックグラウンドを有する人々とのコラボレーションを通じた、インスタレーション作品の制作であった。参加者してくれた人々と京都市内を一緒に歩き、色々なことを語り合いながら、映像や写真を撮影した。移民研究を専門とする若手研究者を招いて、京都芸術センター内にある、廃校となった小学校の教室を会場にしたワークショップも企画した。そのアート・プロジェクトにとって、ほかの多くのアート・プロジェクトと同じく、地域住民や会場を訪れた鑑賞者との「密な」交わりは作品の重要な軸であった。

山本浩貴《他者の表象》(2015年)インスタレーション、撮影 前谷開
京都芸術センターアーティスト・イン・レジデンスプログラム2015
美術批評家の椹木野衣は、ウェブメディア「じんぶん堂」のインタビュー(「泡のように離合集散、「密」だった平成の現代美術 椹木野衣さんに聞く『平成美術』」[1])のなかで、「新型コロナが終息しても、人が密になることへの恐れ、抵抗感が残る。それが人々のコミュニケーションを変える」のではないかという考えを示している。たしかに、コロナ禍以降、例えば高齢者を含む多彩な参加者を招き、たくさんの人々のあいだで行われるワークショップには抵抗感があるだろう。その意味で、新型コロナウイルスはソーシャリー・エンゲージド・アート・プロジェクトを展開していく上での様々な制約をこの世界に残した。
上のインタビューで、椹木はこう続ける。「逆にそれらを糧にして生まれるアートがあるとすれば、それが令和のアートだと思います。例えば、マスクをせずに会話できないということが、生まれた時から当たり前の子どもたちが育っていけば、そこから別のものが生まれるかも知れません。それ以前の密な時代を知っている人たちにとっては、喪失感の方が大きく残り続けるのではないかと思います」。たしかに、次世代のアーティストたちが、そうした制約をバネにアートの新しい形式を生み出していくであろうという考えには強く同意する。そして、「それ以前の密な時代を知っている人たち」(そこには筆者も含まれる)にとって、密なコミュニケーションを通じた作品制作が可能であった時代へのノスタルジーが、根強い喪失感とともに残るという見方にも一定の説得力がある。
だが、旧世代に属するアーティストたちも、そうした喪失感すらも糧にして、新しいかたちのアートを生み出していくことが期待できるのではないだろうか。美術史をふりかえってみれば、アーティストたちはいつも逆境を創造のエネルギーに変換してきた。密な交わりを大切な素材としてきたソーシャリー・エンゲージド・アートについても、きっと同じことが言えるように思われる。
ソーシャリー・エンゲージド・アートをめぐるこうした流れ(あくまでも筆者の予測でしかないが)のなかで、アーティスト・イン・レジデンスが担うことのできる役割は何であろうか。アーティストたちは、これから思いもよらない方法で新型コロナウイルスがもたらした危機を乗り越えるようなプロジェクトを展開していくだろう。その流れのなかで、コロナ以後の新しい形式のソーシャリー・エンゲージド・アートが生まれてくるに違いない。それは、密な身体的接触を避けた別様なコミュニケーションを軸に進められるアート・プロジェクトとなるだろう。オンライン・コミュニケーションを可能とする新しいテクノロジーの力が、これまで以上に存分に発揮されるプロジェクトになるかもしれない。アーティスト・イン・レジデンスとそこでの仕事に従事する多彩な(多才な)人々の存在は、芸術制作の「伴走者」、より適切な言葉を選択すれば「共創者」としてさらに重要なプレーヤーとなっていくはずである。
そうした人々に必要とされるスキルとして、見たこともないソーシャリー・エンゲージド・アートの流れに柔軟に対応しうる流動性や、一見すると実現不可能に思われるプロジェクトを実現可能なものにしていくための創造性などが挙げられる。ときには、アーティスト・イン・レジデンスの側が地域ネットワークや土地勘などのアドバンテージを活かして、アーティストを牽引していくことも必要となるかもしれない。いずれにせよ、コロナ禍の時代を経てソーシャリー・エンゲージド・アートの潮目が大きく変わるとき、アーティスト・イン・レジデンスが果たすことのできる役割はますます重要に、かつ必要不可欠なものになっていくことは間違いない。
[1] https://book.asahi.com/jinbun/article/14295845
山本浩貴(やまもとひろき)
文化研究者、アーティスト。1986年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、ロンドン芸術大学にて修士号・博士号取得。2013~2018年、ロンドン芸術大学トランスナショナルアート研究センター博士研究員。韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラルフェロー、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教を経て、2021年より金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科芸術学専攻講師。著書に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社 、2019年)、『トランスナショナルなアジアにおけるメディアと文化 発散と収束』(ラトガース大学出版、2020年)など。
※本記事は「文化庁 令和2年度「アーティスト・イン・レジデンス事業」オンライン・シンポジウム」に関連して執筆されました。
2024.8.5ヨーロッパでのアーティスト・イン・レジデンスの舵取りの仕方
2024.7.19アーカイブ:AIR@EU開設記念 オンライン連続講座「ヨーロッパでのアーティストの滞在制作・仕事・生活」
2024.6.12Acasă la Hundorf 滞在記 アーティスト:三宅珠子
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕