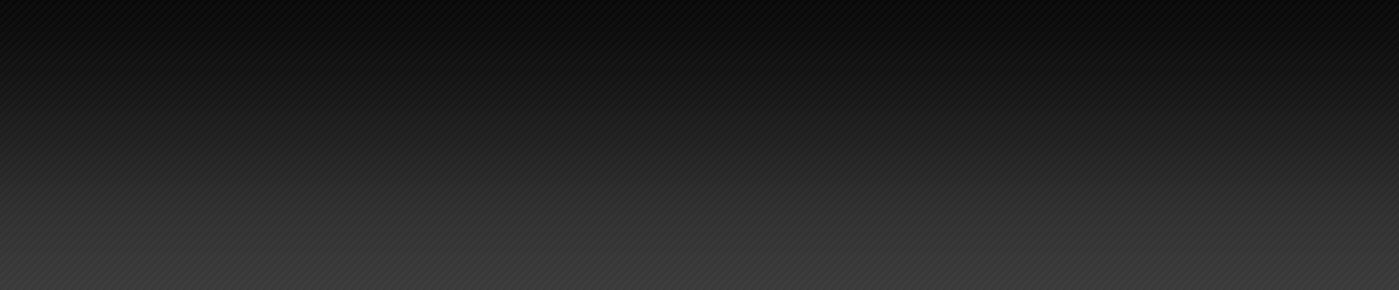

■ジェームズ・ムリウキ■
私はケニア出身で、当初大学でコンピュータープログラムを勉強しましたが、ナイロビ大学に移籍してデザインを専攻しました。そこから写真を媒体に表現していきたいと思うようになりました。この10年から15年の間にケニアでは次なる発展の段階を迎え、都市開発の様子を目の当たりにしたときに、その魂の部分、開発のそもそもの根源は何だろうととを考えました。つまり、例えば女性が出産を間近にした時お腹がどんどん大きくなっていくけど、その中のものは何かよくわからないというような、そんな不安を感じたんです。次々と立ち並ぶ近代的な建物の、ガラスなどの原材料がどこから来ているんだろうと考え、そこから、ケニア各地にある石の採掘所などの土地を訪れるようになりました。
土地は、ケニアのアイデンティを理解するために非常に重要なものです。1963年にイギリスの植民地から独立し、社会が混沌としていて仕事もない、お金もない中で、土地を所有しているということが非常に社会的な担保になりました。土地を持っていないということは根っこがないと見なされるほど、土地や土そのものとケニアの人々のアイデンディティは強く結びついています。自分の所有地に家族や先祖を埋めるという土とのコネクションは、所有物というだけではない繋がりがあるのではないかと考えています。

James Muriuki《Untitled》
今回のテーマであるアーティスト・イン・レジデンス(AIR)についてお話すると、経験した中でも、2011年にコペンハーゲンに滞在したことが非常に印象に残っています。当時私はまだデザインの勉強をしていました。実際にアーティスト、キュレーターとして専門的な知識を持つ人たちと1ヶ月間滞在をして、いわゆるアカデミックな、訓練されたアーティスト、キュレーターとはどういうものなのか、どういう活動をするのかということを知るきっかけになったんです。
その時には、ケニアとデンマークの関係性を見出すことを糸口に制作活動をしました。そこで、デンマーク人のカレン・ブリクセンの『アフリカの日々』という小説(後に『愛と悲しみの果て』というハリウッド映画にもなった)を知り、彼女をテーマに『Not About Karen Blixen(カレン・ブリクセンについてではない)』という展覧会を企画しました。1940年代にケニアがどう描かれているのか、ということから、その当時のケニアの需要というか、ケニアがどう世界の中に位置づけられていたのかが分かってきましたし、そこから現在のケニアが置かれている状況についても考えることができました。ケニアの歴史についても、植民地時代が長かったことからついついイギリスとの関係のみで語られることが多いのですが、実はイギリス以外の国とも関係性があったということが歴史の中から見えてくる。そこに気づくことができたのは、AIRのおかげだったと思います。

James Muriuki《Not About Karen Blixen》
2012年には「Art in Local Health Project」というAIRに参加しました。世界のアーティストと医療リサーチセンター、つまり医療とアートを繋げる試みをしているロンドンの団体のプログラムでしたが、実際の滞在はケニアでした。ただし、自分が住んでいるナイロビではなくて、全く別の地域です。ケニアには40ちかくのコミュニティがあり、それぞれに言葉も生活習慣も違うので日頃の生活の中では互いに出会うことはありません。このAIRを通してケニアの「地元の人たち」と出会うことができたと同時に、同じケニア人であっても自分と異なる人と、アートを媒介にして出会うことができました。AIRというと海外に行ってアートの経験をしてくると考えがちですが、まだまだ自分の国の中でできることがあるのではないかということに気づかされました。
また、ドイツのバイロイト大学の社会学研究者と、ケニアにおける中流階級の状況について考えコラボレーションするAIRにも参加しました。彼らとのコラボレーションを通して違う国の人々とコラボレートするだけではなくて、社会学というアートとは別の分野の専門家とコラボレーションすることができました。そこではまず、社会学とは何か、階級とは何かという、普段アートの文脈では上がってこないようなキーワードを与えられました。そうした社会学的な定義から、アーティストとして何ができるのかを考えてつくったのが、ナイロビの中流階級の人々の家に行って写真を撮ったシリーズです。一枚で中流階級を一般化することはできないので、膨大な数の写真になったわけです。
ザンジバル(タンザニア)にザンジカという地域があります。そこでのAIRにも招待されたことがありました。AIRの中には体系的に資金もあってスタッフもいて、きちんと整えられたプログラムがある一方で、まだまだザンジカのように発展途上にあってスタッフもいなければリソースもない、というものもあります。でも、そういったAIRに行った時、リソースが限られているから何もできないのかというかというとそうではなくて、きちんとした作品を作ることができました。まずGoogleでザンジバルを検索してみると、観光、ツーリズムのイメージがたくさん出てきます。でも、考えたら分かると思うんですけども、みんながこういう暮らしをしている訳ではないですよね。そこからヒントを得て、実際のザンジカの人々の生活に焦点を当てて、色んな家庭を訪れて写真を撮らせて頂くことで、Googleのイメージ、いわゆる一般化されたイメージと実際の人々の生活のギャップを可視化しました。
■リュウ・リュウシャン■
-人生における移動-
5年ほど前に京都芸術センターでAIRに参加しました。私にとって人生の最初の大きな移動は、10代の時に両親と一緒に日本に移住して来たことですが、1つの国からもう1つの国に渡るという旅の経験は、身体的な移動だけではなく、精神的な変化も伴う体験でした。当たり前だった自分の故郷の景色、そこでの生活が身体的に移動することによってガラリと変わり、自然と2つの国、2つの文化、2つの言葉が自分の体に宿るようになってきました。その国での暮らしやコミュニケーションなど異なるところがたくさんあると思いますが、そういうことを体験する中で自分自身が何者であるのか、どういうアイデンティティを持つ存在なのかということを考えたり、些細な日々の問いかけがいつの間にか何か表現したいという想いに変わってきたのではないかと思います。

リュウ・ルーシャン「私と京都の物語」(2013年)
2つ目の移動は17歳の時にカナダの高校に長期留学したことです。日本で授業を受けていたとき、ショートカットなんだけど一ヶ所だけ伸ばして三つ編みをしている、とても面白いヘアスタイルの女性の先生に出会いました。興味をもって彼女の話を聞いたら、彼女は色んな国に行ったことがあり、その中で多文化主義国カナダについても紹介してくれました。その話を聞いて、私も早くカナダに行きたいと思うようになり、翌年には留学することになりました。カナダの教室には色々な国籍の人たち-イギリス、韓国、インド、エジプト、日本、中国-がいました。様々な文化背景を持つ移民や、カナダ人ではあるけど元々は韓国や中国出身など、多様な帰属意識の在り方について体験しました。彼らと自由な議論ができたことがとても貴重な経験で、表現へのさらなる想いになりました。こういった体験からこれまでの自分の色んな悩みやアイデンティティについても考え、整理されていくという開放感がありました。
3つ目はヨーロッパへの移動でした。大学を卒業して、このまま企業に就職するかと考えていた頃に、やっぱり自分は何か表現をしなければいけないのではないかと思い始めて、はじめてドキュメンタリー作品をビデオカメラで創作し、それがヨーロッパの国際映画祭に入選しました。そこからイギリスに芸術留学して、そこで今まで自分が考えていたようなアート-絵画、音楽、演劇といったもの-ではないものを目の当たりにしました。また、移民、マイノリティのエンパワーメントに繋がる芸術活動に対して、イギリスなどでは肯定的な評価があることを知りました。やがてイギリスのアーツカウンシル、チャイニーズ・アートセンター・マンチェスターなどを通じて、移民と難民の記憶を記録するような映像作品や文化芸術へのアクセスによって居場所を確保するコミュニティアートの活動に対して支援を受けることができるようになり、そこで初めてAIRについて知るようになりました。
-AIRに参加する意義-
1つは異分野の表現者がお互いの活動について知り、刺激しあえる、創作活動の実験の場となるということです。例えば、ダンサーで、オーストラリアに住んでいる中国系のアーティストの方と、イギリスにいた中国系のアーティストである私とで、プラットフォームチャイナというAIRに参加したことは、異なるバックグラウンドのアーティストによる共同創作の貴重な機会となりました。
もう1つの機能として、先ほどジェームスさんもおっしゃっていたのですが、国とか言葉とか、そういったものを越えて一人の人間として出会うということ。それはマスメディアを通した知識とは異なります。そこでは、私たちがどこの国の出身で、どういう政治的バックグラウンドを持っているかということよりも、一人の人間として、face to face でコミュニティの中で抱えている問題、また国際的な問題を共有する場になります。これまでの滞在先で私は様々な国の移民、難民、マイノリティと出会い、彼らの体験を知ることになりました。彼らの感情や記憶を記録し、エンパワーメントに繋げられるような活動に取り組みました。例えば、韓国で国境のない村として知られるアンサン市の外国人集住地区のイトマスコミュニティセンターでAIRに参加しました。ここで出会ったアーティストは、日本の統治下時代に、両親と共に韓国から満州へ渡り、終戦後中国に70年間残留して、中国共産党の国家建設に参加したという経験を持っています。その後ソウルオリンピック以降にできた永住帰国支援事業によって初めて韓国の国籍を取り戻すことができたそうです。彼らの移住の物語を私はオーラルアーカイブとして記録して、《落葉帰根》という、落ち葉が根に戻るというタイトルの作品にまとめました。
最後にもう1つ、滞在先のコミュニティの住民と共に学び、そして領域を横断するような対話を通じて共存空間を作ることも、AIRの役割なのではないかと思っています。実際に、私は京都芸術センターのプログラムでパフォーマンスワークショップを通じて市民にパフォーマンスの理論と実践について紹介し、参加者たちは「私と京都の物語」と題し自身のライフストーリーを元にしたパフォーマンスを京都各地で発表しました。この活動を東京の「小金井アートフル・アクション!」で報告したことがきっかけで、東京でもこういった市民の為の活動をできないか、と声がかかり、今年から「多文化アートプラットフォーム」を結成して東京に住む住民のためのワークショップをしています。パフォーマンスだけではなくて、対話を通じて映像作品、パフォーマンス、美術、絵画など様々な分野の表現活動が生まれる場となりました。
AIRを終えた後も「私と京都の物語」の中で出会った参加者たちとは繋がりがあります。このプロジェクトで表現活動と出会ったある統合失調症を持つ女性はその後自分の病について本を自主出版し、自分自身の体験を元にしたオーラルヒストリーを他者と共有するようになりました。ある音楽が好きな男性は、その後ヨーロッパの演劇祭で作品を発表するようになりました。また別の女性はこれまでにセックスワーカーとして働いた経験があり、その体験を元にしたパフォーマンスを発表するようになりました。こうした繋がりは、私自身にとっても大きな学びとなり、そして大きな励みとなりました。
最後に、私は近年インドのラジャスタンという砂漠地方で「Sewing Seed」というアーティストキャンプのプログラムに参加しています。このAIRは、ワークショップとゲストトーク、プレゼンテーション、パフォーマンスから構成されていて、街の人々と一体となってイベントを進行していきます。現代アートに触れる機会のない、貧しい農村地方の子供たち、女性たちと共に, 彼らの普段の記憶や、社会問題をテーマとするパフォーマンスをしました。この活動は、今後も続けたいと思っています。
-AIRの問題点-
私は日本の児童養護施設や障害者施設、病院などでの活動も経験したことがありますが、そうした活動は、社会的なニーズ、需要があって必要とされているにも関わらず、実際にはそういうAIRプログラムはほとんど存在していません。ギャラリーやアートセンターなどが存在していない場所、そうした社会の隅々でプロジェクトを実現するためのサポート体系をどのようにしたらいいのでしょうか。また、現在のレジデンスプログラムは数週間から2ヶ月といったものが多いのですが、コミュニティにコミットするのであれば継続性が必要であり、数年単位で取り組みをしたい場合に、どのような方法、考え方があるのかということです。私はインドのAIRを通じて地域の人と会って、この地域を日本の子どもたちに紹介したいと思いました。そこで再度訪問して、日本の子どもへの教材として映像をまとめたのですが、アートはアートのためだけではなくて、教育などの分野でも転用できる、あるいは総合的な交流の可能性があります。国際的な広がり、継続的な活動を実現するには、アーティストの力だけでは足りません。今後オーガナイザーや教育者、文化人の方々と議論する必要があると思います。
■三原聡一郎■
-非日常を得る、常識を無くす/増やす-
これまで、5カ国6ヶ所に滞在してきました。AIRとは何かを一言では言いにくいんですが、僕の中では旅以上住まい以下のようなものだと思っていて、新鮮さを保ちつつ、かつその時だけの印象に留まらない不思議な時間感覚だと思っています。 最初に行ったのは台湾の国立台北芸術大学の中にある關渡美術館(Kuandu Museum)でのAIRです。その後に行ったのがトーキョーワンダーサイト(現トーキョー・アーツ・アンド・スペース)の公募でベルリンにあるクンストクオーター ベタニアンです。ここは結構大きなスタジオで充実した制作ができました。個人的に好きな土地に行ったのが、チェコのヒルゼンという街で、詳しい方は分かると思うんですけど、あるビールのスタイルのうちの一つがここから始まったという街です。そのビールを飲むために死ぬまでにいつか行かないといけないなと思っていて(笑)、公募が出た時に僕が行くしかないとアプリケーションを書き、選ばれてとても嬉しかったです。これは遊工房アートスペースが公募をしていました。その他では、山口市のドゥー・ア・フロントという空き家をテーマにしたAIR、「対馬アートファンタジア」という滞在を含めたグループ展企画などにも参加してきました。
改めて自己紹介すると、多摩美術大学を卒業後、IAMASというメディアアートに特化した教育機関に行き、その後に山口情報芸術センター(YCAM)で技術スタッフとして、エンジニアキュレーター、サイエンティストといった人たちと一緒にアーティストの作品制作や技術リサーチなどをサポートしていました。2014年からは自身の制作活動をメインに、海外や、日本では京都芸術センターの制作室を使わせて頂いています。音が好きで、美術と音楽との境界にあるサウンドアートから始まって、リアルタイムに制御可能な素材を扱って作品を作ったり、また今は、生命に興味を持っています。
1つだけ作品を紹介すると、《moids》というインスタレーション作品は一見ものすごく複雑そうに、ケーブルが絡んで見えるんですけど、同じ機能を持った音響基盤が1024個あるだけなんですね。その一つひとつが何をしているかと言うと、音を感知したら音を出すということだけです。それを空間に配置すると、音のドミノみたいな現象が起きる。設定したプログラムとかではなくて、ただ個々の機能がお互い近くにあるものの音を繰り返しているということだけで成立している音環境みたいなものです。来場者の立てる物音にも反応したり、自然とテクノロジーの関係性みたいなものを体験も含めて提案しています。震災で原子力発電所の事故があった時に、自分の制作素材に電気を使っていたのに電気自体について全く制作の中で考えていなかったなということを思い、エネルギーと生命に興味を持ち始めました。
そういう流れで、文化庁の新進芸術家在外研修という制度で「シンバイオティカ(SymbioticA)」という西オーストラリア大学の生物学の実践をアーティストに開放してくれるラボに一年間程在籍しました。生命科学の実践をできる場所はかなり限られているんですが、ここではクリーンベンチ(外界のカビなどが入ってこないクリーンな状況で作業ができる、菌や細胞の培養をするためのスペース)などをアーティストに開放しています。僕は生命と物質の境界、卵の殻だとか自分の皮膚だとか、そういう素材に興味があったので、「Nature」誌に載っている、自分の抜いた髪の毛から皮膚を増やせるというプロトコル(手順書)を参考に、自分のヒゲとか髪の毛とかを抜き数秒以内に培養液に浸しその培養液のレシピを2時間以内に何回か繰り返すとか、一週間経ったら違う培養液に変えるとか、そういうステップの繰り返しで皮膚細胞が増えていく。例えるならすごく厳密な料理みたいなもの、そんなことをずっとやっていました。
また、オーストラリア滞在中には砂漠地帯の北部にラボのみんなでリサーチトリップに行きました。そこには、初めて地球上に酸素を供給したと言われる8000年前、1億年前の原始的な生命の形状が未だに生きて残っている場所があるんですね。さらにヘリコプターをチャーターして島に行くと、1950年代にイギリスが核実験をした島があるんです。ここの土壌のリサーチをしに行き、実際野生動物がどれくらい残っているか、50数年間人の手が離れた島がどうなっているのか、そんなことを見て来ました。そこで、色んな自然観に触れたことで土自体にすごく興味を持ったんです。その頃偶然、あるウェブサイトで土の中にいる微生物が発電するという記事を見かけて、微生物燃料電池というまさに僕が探していた生物とエネルギーの両方を共存させて、しかもそれ自体が生きているというおもしろい現象を見つけて、色んな展開を試したり「自作で作っているんですけど色々アドバイスして下さい!」と無理やり研究者を訪ねたりして、少しずつ成果になっていって、2016年の「茨城KENPOKU芸術祭」や「Media City Soul」に出したりしました。今は苔と土を使ったアプリケーションで試行錯誤しています。2016年の初めには、京都芸術センターの15周年企画で和室で展示を実現できたり、また「DOMANI展」では、今までの微生物燃料電池の土のサンプルや、形にする過程で開発したデバイス、実験素材、苔の培養のトライアルを展示しました。

三原聡一郎『空白に満ちた世界』(京都芸術センター、2017年)
今応募しているAIRが「ars bio arctica Residency」というフィンランドのラップランドにある、僕が調べた中では最も北極に近い場所にあるAIRで、ヘルシンキ大学のアートラボで空きがある時にアーティストを受け入れているもの。もう1つは「ラブヴェルジ(lab verde)」といって、アマゾンの環境を保全する為の自然科学の研究所です。今年初めて国際公募になって、専門家しか行かないようなアマゾンの研究所にアーティストを連れて行って、専門的なディスカッションを一週間かけて行うプログラムです。先ほどのジェームズさんのお話と近いんですけど、今は芸術が芸術単体として存在するというよりも、広い他の専門分野の方から芸術家を呼んだり、芸術のフォームを利用して何かアクティビティをする、ということが起こっているんですよね。芸術が何かものを作るっていうことよりも、世界を独自に観察しハッピーな何かを提供するためのものであればと思っています。専門家の方も、思いも寄らなかったことをきっと芸術家ならしてくれるだろうと思っているんですね。それが、芸術の形式ということは置いておいたとしても、最も自由な人間の振る舞いの方法だと感じていて、それを広く芸術として、美術の名の下に共有できる環境があるんだったら、それはとても重要なことのような気がしていています。

シンポジウムの様子
日沼禎子:ありがとうございました。このテーマは「移動することと創造活動」ということで、それぞれの流動性について、具体的なご経験の中からお話頂きましたが、アーティストとしてのキャリア、自身の可能性を広げる、発展させていくということについて、AIRの意義についてもう少しお話しいただけることがあれば、一言ずつお話をお聞きしたいと思います。
ムリウキ:三原さんとリュウさんの話を聞いて非常に自分も共感するところが多くありました。ということは、つまり出身国に関わらずアーティストとしての共通点もしくは人間としての共通点があるからだと思うんですね。キャリア形成の話ですが、こ自分がどういうアーティストでありたいか、どんなアーティスト活動をしているかということによっても違うのかも知れません。私自身はメディアを限定せずに活動していますし、1つのテーマでもなるべく色んな角度からアプローチを探していくということを活動のコンセプトにしているので、そういう意味でAIRを通して様々な人に出会い、色んなメディアに出会い、それから様々な異なる分野の人々と交流しています。それが作品という形にならなかったとしても、アーティストとしての経験値や考え方に及ぼす影響というのは計り知れないと思います。だからと言って自分が持って生まれたものを忘れて新しいことばかりを探すのがAIRの目的ではなくて、自分がどこから来て、どこに行けるのかということを探す場所だと思います。AIRは新しいネットワークに目が行きがちですけども、自分について再確認できるのがAIRならではの経験だと思います。
リュウ:今の時代の中で、アイデンティティをもう少し広い視野で見た時に、今この地球に生きている一人の地球人としての視点を考える。そして、情報化時代の中で何が本物なのか、何が真実かをみんなが探している中でアーティストはその先頭に立って考え、新しい生き方、新しい世界観、それを共に探求して行くような思考の場を広げていく。それは創造の意義そのものに関わることで、アートの外部に存在しているという風に私は考えています。私自身もAIRを通じて世界を知るということを体験しました。これからも多くの人たちと世界を広げていけるように活動をしていきたいと考えています。
三原:お話をお聞きして、芸術が指し示すものが本当に広範にわたる状況になっていると思いましたが、実際に芸術という名の下に何か企画するということになると、具体的な場を作ったり、人を集めたり、そういうことが必要になってくるんですね。それが、既に今までのように美術史を学べばできるというようなレベルではなくなりつつあって、これからは、芸術は人々が拡張していくべきものだと思います。そういう拡張された新たな分野ができつつある時に、自分がしてきたような経験が少し活かせるのではないかと思っています。
日沼:ここでは、一人ひとりのアーティストが活動してきたことや様々なAIRをめぐるお話しを聞きましたが、世界に存在しているAIRのプラットフォームを運営する側の活動やネットワーキングについて、第二部で聞くことができればと思います。
「第2部:ネットワークの活用」に続く
James Muriuki (ジェームズ ムリウキ)
1977年ケニア、ナイロビ生まれ、ナイロビ拠点のアーティスト、キュレーター。写真や映像、サウンド、インスタレーションなどの多様なメディアを用いて、急速に発展する都市空間の変容を捉えた作品は、国内外で展示・収蔵される。主な展覧会に、「About Time」(Stone town、ジンバブエ、2016)、「Future Africa Visions in Time」(Iwalewahaus、レバノン、2016)、「Making Africa」(Guggenheim Bilbao、スペイン、2015)、「Who is the City」(Swedish Centre for Architecture and Design、スウェーデン、2013)、「Layers」(Nairobi National Museum、ケニア、2012)など。
劉 璐姗(リュウ ルーシャン)
アーティスト。中国北京生まれ、東京在住。ロンドン芸術大学ウィンブルドン校修士課程修了。東京藝術大学大学院 映像研究科メディア映像博士後期課程修了。国境・多文化・移民・子ども・女性・マイノリティ・貧困・メディアなどのテーマに関心があり、映像・パフォーマンス・コミュニティアートによる表現活動や多様性理解につながる教育研究活動を実践してきた。これまで中国、韓国、インド、日本などでAIRに参加。京都芸術センターのプログラムに2012年に滞在制作を行う。市民向けパフォーマンスワークショップを企画した。
三原 聡一郎(みはら そういちろう)
アーティスト。京都在住。音、泡、放射線、虹、微生物、苔など多様なメディアを用いて、世界に対して開かれたシステムを芸術として提示。2011年より、テクノロジーと社会の関係性を考察するために空白をテーマにしたプロジェクトを国内外で展開中。日本を含め5カ国経験したAIRの中でも西オーストラリア大学のバイオアートラボSymbioticAでの滞在制作では医学、生物学を跨いだ芸術実践を行う。近年の個展に、「空白に満ちた場所」(京都芸術センター, 2016)、グループ展に「科学と芸術の素」(アルスエレクトロニカセンター, オーストリア, 2015−16)、茨城県北芸術祭(常陸太田市エリア, 2016)など。
日沼 禎子(ひぬま ていこ)
女子美術大学准教授、AIRネットワーク準備会事務局長。1999年から国際芸術センター青森設立準備室、2011年まで同学芸員を務め、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアーティスト支援、プロジェクト、展覧会を多数企画、運営する。さいたまトリエンナーレ2016ではプロジェクトディレクターを務めた。2013年より陸前高田AIRプログラムディレクター。
2024.8.5ヨーロッパでのアーティスト・イン・レジデンスの舵取りの仕方
2024.7.19アーカイブ:AIR@EU開設記念 オンライン連続講座「ヨーロッパでのアーティストの滞在制作・仕事・生活」
2024.6.12Acasă la Hundorf 滞在記 アーティスト:三宅珠子
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕