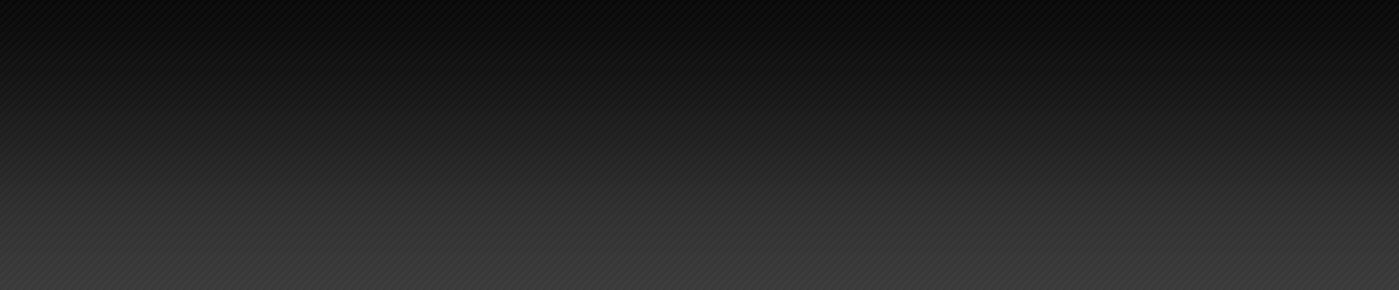

マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー(ドラマトゥルク)
「地球上のある地点まで最大の距離を保てるのは、その場所を離れる瞬間である。なぜならその場所から進むどの一歩も、再びあなたをその場所へと近づけるから」。フランスの作家で、哲学者でもあるヴィクトル・セガレンは1903年に東アジアとポリネシアを旅行していたときに、この空想的な考えを語っている。セガレンは「エキゾチシズムの周旋人(proxénètes de l’exotisme)」にならずに異なるものを経験することを目的とした最初のヨーロッパ人であると考えられる。この引用句の翻訳において見えなくなっている小さいが重要な違いは、ドイツ語の「erfahren」には「経験する」という意味だけでなく、文字通りの意味で「あちこち移動する」という意味もあるということである。

マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー氏
河童の瞬間
私はすでにいくつかの同時代の日本人のステージや視覚芸術を見たり、私の専門的職業であるプログラム制作の仕事において日本出身のさまざまな芸術家と一緒に働いた経験があったのだが、2011年7月に森下スタジオに滞在する以前の私のもっとも強い知覚的記憶は、2004年に沖縄の南端から北海道の北の国境まで行った6週間の旅と結び付いていた。
私はいまでもこの日のことは鮮明に覚えている。遠野で食料品を買っていたとき、誰かが叫んでいるのが聞こえた。「ねえ、あなたヨーロッパの人でしょう、少しお話しできないかしら」。結局、ご主人とともにこの田舎に移ってきたばかりの元BBCジャーナリストと一緒に、車で4時間の旅をすることになった。この予期せぬ出会いの微妙な部分は──旅行に備えてこの地方の民話をすべて読んだ後で──われわれが神社で男根像のような巨大な石の前に立っていたとき、私が発狂しそうだったことである。私は自分がいま、河童の明らかな標的であり、私の命は刻一刻と終わりに近づいていると確信していた。
なぜこのような個人的な話をするのか。それは最近のリサーチ中に私が再び経験したことについて、ある視点を与えてくれるかもしれない。つまり「あなたは未知の異なるものしか信奉することができない」ということである。仕事で旅をしているときは、ほとんど常にショーを見るとか、会議あるいはフェスティバルに参加するといった理由や任務がある。しかし、ただ東京にしばらく暮らして、自分のスケジュールに従って会いたいと思っていた人に会うという贅沢が許されると、あらためて自分の職業について考え直させられる。それは文化や芸術的シーンを概観したり、味わうというばかげた考えに関することではなく、すべて選択に関することである。すなわち、2つのショーの合間に慌ただしくディナー・ミーティングを行なうのではなく、興味のある人と3回ランチをするとか、ある特定の目的──フェスティバル、ショーケース、コラボレーション──に関して最適な「対象」を見つけようとするのではなく、単純に芸術家、活動家、興味深い人々と時間を過ごすというような選択である。
セゾン文化財団のチームは非常に協力的で、私が話し掛けるべき適切な人を探す手助けをし、必要があれば通訳もしてくれて、私が必要とするときはいつでも手を差し伸べてくれた。私は孤独を感じることも、途方に暮れることも一切なく、その一方で、監視されていると感じたことも一度もなかった。彼らが森下スタジオでつくっているのは小さな魔法の王国である。提供される場所は素晴らしく、必要な物はすべてそろっており、立地も完璧で、渋谷、新宿、池袋といった繁華街ではない。私はそういった場所が嫌いなのではなく、そういった場所は自分の典型的な型にはまったものをそれで良いと信じさせてしまう力が強いのである。わずかな苦みがあるとすれば、二人のルームメートとあまりつながりを持たなかったことである。しかしその混ざり具合は申し分なく、私はいまでも隣りの部屋で演奏されていた琵琶の音が耳に残っている。
日本に来た後の国内での移動は、セゾン文化財団が提供しているもうひとつの素晴らしいことである。京都を訪れて、現代の狂言を見たり、大阪に行って、素晴らしい塚原悠也のエキシビションのほぼプライベートのオープニングを訪れただけでなく、近いところでは、個人の家での打ち合わせや、自分自身ではけっして知ることのない場所へと移動した。ある晩、素晴らしいディレクターであるタニノクロウ氏が、彼の車で都内のドライブに連れて行ってくれた。われわれは東京湾で車を止め、キャンドルで創られたいくつかの大きなサインの前に立った。誰にもそれらの意味は説明できなかっただろうが、私はまたもや河童の瞬間を経験した。今回は恐怖ではなく、純粋な暖かさと美しさを経験した瞬間だった。
永久的危機のなかで暮らす
私のリサーチの目的は、誰々がどこの出身であるか、その人がなにをしているか/していないか、経済、財政、社会的ニーズによりどのように関係が形成されるか、といったようなことは意味を持たない、一緒に時間を過ごすための瞬間を創造することであった。芸術分野は作品あるいは人々に関する言葉、記述、描写を探すことにおいて非常に早急であり、芸術家をその作品の代表、さらに悪いことには文化に単純化する傾向がある。私はこの分野で仕事を始めて以来、常にこの層を除去することに関心を持っていた。私は滞在期間中にこのことを経験でき、スイスで芸術文化センターを監督するという新しい仕事を始めたばかりではあったが、もっと時間を取れなかったことをいまでも残念に思っている。
社会に対して批判的な見方をし、また自分の美学に対する社会の見方に批判的であることを恐れない若い芸術家や思想家に注目することで、私は自分のリサーチにおけるもうひとつの赤い糸を再発見した。私が日本に着いたのは3.11のわずか数カ月後だったので、社会や社会における市民の役割について至るところで議論がなされていた。自然の持つ力、その力の結果については誰も語らず、それら要素に対する人間一人一人の関係について議論されていた。私はそのとき、日本人は自分たちが危機的状況のなかで暮らしている、それはバブル崩壊後の経済危機や、3.11後の原発危機ではなく、その言葉に本来備わっていた意味での永久的危機のなかに暮らしていると考えていることを実感した。古代ギリシャ語のクライシス(κρίσις)は、意見、推定、その結果として決定を表わしている。
これは、私個人だけでなく、西欧人も日本から学ぶべきことである。永久的に決定している状況は、人をより冷静で、より感謝の心を持ち、より人のことを思いやる人間にする。
今回の旅に由来する最初のコラボレーションがスイス、ルツェルンの小さな山村で私が運営しているSÜDPOLに登場するとき、こうした感情のいくつかを還元できることを心から期待している。パフォーマンス集団「悪魔のしるし」の危口統之氏はここに数日滞在し、工業高等学校の生徒とともに搬入プロジェクトを実施し、チューリッヒ、バーゼル、ルツェルンというスイスの3都市を巡回する搬入彫刻へと発展させる予定である。危口氏の仕事は、大きな意味での芸術と社会の関係、具体的な瞬間という意味での芸術家と観客の関係を、非常に賢いやり方で問うている。それはこの経験の一部であるすべての人々に、いわゆる抽象世界にとって、あなた自身の方向性や思考がいかに重要であるか、世界規模の決定に対して責任ある人間であるということがいかに具体的なことであるのかを実感させる。
誰が芸術センターを必要とするか
ヨーロッパ、特にドイツ語圏文化において、われわれは大きな課題、すなわちオペラ、バレエ、美術のようなトップダウンの芸術と、演劇、公共の場でのアート、あるいはデジタル/バーチャル・アートのようなボトムアップの芸術がひとつにまとまらないという大きな課題に直面しているが、日本でのジャンルの扱い方ははるかに遊び心に満ちている。伝統あるいは古典的様式に誠実ではないという意味ではなく、ある特定の決定により人が導かれるさまざまな方向性に対してオープンであるという意味で、遊び心に満ちている。ヨーロッパでは、経済状況がはるかに良かった数年前と比べて、年老いたエリートたちは再び保守化傾向を強め、新たな境界を持ちこみ、なお一層守りを固めようとしている。新鮮な決断や方向性が最終的に西欧をどこか面白いところに連れて行く可能性があるかもしれないのに。
SÜDPOLの建物の隣りは、トレーラー、テント、自家製の木造建築に暮らす約30人の落ちこぼれ志望者の非公式の集落である。彼らの哲学は60年代に遡っており、生活する一定の構造としての社会を拒絶し、社会を疑問視しようとしている。私が現時点で言うべきことは、彼らがわれわれの家の施設を利用し、SÜDPOLから電気を引いていることである。坂口恭平氏は夏に彼らと共同作業を行なう。話をし、議論し、アイディアを生み出す。坂口氏の「0円社会」というアプローチは、「どのように暮らしたいか、そのためにはなにが必要か」といった質問を非現実的に考えるのではなく、現代という側面から考えるのである。坂口氏から、「社会はますます高齢化し、人口が減っているので50年後には住宅スペース全体のおよそ半分は空き家になる」という彼の考えを聞いたとき、隣りに住む若者たちの子どもの時代には、私がいま椅子に座って、この一節を書いているこの部屋に暮らすことがはるかに楽になっているだろうと私は気が付いた。「そのころ、誰が芸術センターを必要とし、それはどのようなものになっているだろうか?」。

坂口恭平氏とのリサーチ風景
マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー
1981年ドイツ・デッゲンドルフ生まれ。アーティスティック・ディレクター(ルツェルン・SÜDPOL)、ドラマトゥルク。メディア・スタディーズ、インターラクション・アンド・プロセスデザインを学び、その後ドラマトゥルギーで修士号を修める。2008年、HAU(ベルリン・ヘッベル劇場)やロッテルダム市立劇場にてクリス・コンデック演出の『Loan Shark』、ウィーン・フェスティバルやHAUにてバーバラ・ウェバー演出の『リア王』などのドラマトゥルク。2009〜2010年、「Theater der Welt 2010」のフリー・レイセンのアーティスティック・コラボレーター、ドイツ銀行が支援するアート・プロジェクト「A Globe For Frankfurt and the World」のアーティスティック・コーディネーターを経て現職。2010年11月、国際交流基金の招きで来日。2011年、セゾン文化財団のヴィジティング・フェロー・プログラムで再来日。
—
推薦者のことば(事業担当者より)
稲村太郎(公益財団法人セゾン文化財団プログラム・コーディネーター)
セゾン文化財団では、2011年より、現代演劇や現代舞踊の海外ネットワークの拡大、相互理解の促進を目的に、「レジデンス・イン・森下スタジオ、ヴィジティング・フェロー」というレジデンシープログラムをスタート。このプログラムは、芸術家を招へいするアーティスト・イン・レジデンスとは異なり、海外で活躍している舞台芸術のプレゼンターやプログラム・ディレクター、キュレーターなどのアーツ・アドミニストレーターを招へいし、日本の現代演劇や現代舞踊の状況や魅力などを発見していただく機会を提供しています。
そして、2011年7月、栄えある一人目のヴィジティング・フェローとして、マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー氏をお迎えしました。マックス氏は、フリーランスのドラマトゥルクとしてドイツを拠点に活躍後、ドイツ国際演劇協会が主催する「世界演劇フェスティバル」の共同プログラムキュレーターを経て、昨年、弱冠30歳で、スイスのルツェルンのSÜDPOLの芸術監督に就任されるなど、今後の活躍が期待されるアーツ・アドミニストレーターです。マックス氏は、「ラべリング──国際的な芸術をどのようにとらえるか」という研究テーマのもとで、当財団のプログラムを通じて、舞台芸術というジャンルにとらわれることなく独自のパフォーミング・アーツの視点で、演劇、美術、建築、また、クロスオーバーに活躍するアーティストや関係者と交流を深め、日本とのネットワークをさらに拡大しました。また、滞在中、ヨーロッパ・ドイツ語圏の舞台芸術の状況をお話しいただく、パブリック・トークを開催しました。緊縮財政政策により公共劇場が大幅な予算削減を迫られる厳しいヨーロッパの現状のなかでSÜDPOLの芸術監督に就任されたマックス氏から、いかに新しい舞台芸術を打ち出していくのかというアイディアのプレゼンテーションがあり、参加者からの積極的な発言により、グローバルな視点でこれからの舞台芸術について考える試みが行なわれました。
当財団のヴィジティング・フェローの特徴は、海外と日本との交流をうながす「出会い」を支援することです。当財団のネットワークを活用し、フェローの要望するリサーチの内容に応じて、フェローと相談しながら、日本での滞在スケジュール、インタビューやミーティングをアレンジしています。そのため、フェローによって、プログラムの内容は、千差万別です。また、滞在拠点の森下スタジオは、常時、現代演劇や現代舞踊の公演稽古、ショーイング、ワークショップやシンポジウムなどのアクティヴィティが行なわれている場で、日本の現代演劇、現代舞踊のアーティストや関係者が集う、とても刺激な環境だと言えると思います。
2012年は、ヨーロッパ、北米、中近東、アジアなど、多種多様な文化的背景を持つヴィジティング・フェローを招へいする予定で、今後も、海外とのネットワークをつなぐ拠点として、日本の舞台芸術の振興に貢献していきたいと考えています。
[2012年3月31日]
参考:
AIR_J>SEARCH>レジデンス・イン・森下スタジオ ヴィジティング・フェロー
2024.8.5ヨーロッパでのアーティスト・イン・レジデンスの舵取りの仕方
2024.7.19アーカイブ:AIR@EU開設記念 オンライン連続講座「ヨーロッパでのアーティストの滞在制作・仕事・生活」
2024.6.12Acasă la Hundorf 滞在記 アーティスト:三宅珠子
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕