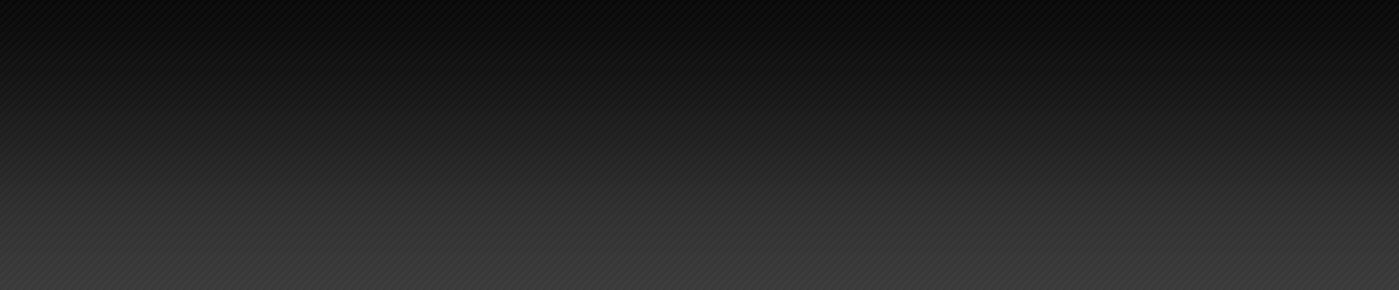

小田井 真美(アート・プロデューサー、NPO法人S-AIR所属)
S-AIRは、1999年に、札幌市内の美術関係者、アーティストにより実行委員会として北海道で初めてのアーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」)プログラム運営団体として発足し、2004年7月にNPO法人化、08年度に活動10周年を迎えました。この10年間で、通算27カ国、57名の海外、国内のアーティストを札幌に招へいしました。
S-AIRの奇跡と軌跡──なぜ札幌でAIRが始まったか
札幌在住のアーティストであり現在S-AIRの理事である端聡(はた さとし)が、1995年、ドイツ学術交流協会(DAAD)の招きでAIRプログラムを体験して帰国。周囲の仲間に、AIRプログラムがアーティストにとって有意義なものであり、札幌で実現できないかと話したことがきっかけだと聞いています。端の友人であった山本謙一(実行委員会代表:当時)はAIRの実現のため各方面に奔走し、柴田尚(代表理事:現在)と事業を開始しました。当時、日本ではAIRの黎明期にあり、運営のモデルを欧米に求め、日本における AIRプログラムの存在意義を模索していた時代でもあったとのこと。設立当時から、「AIR事業はまちづくり的な視点でも社会との接点を目指して芸術活動と社会の有用な関係性を導く可能性がある」と見極めていた山本が、S-AIRの活動理念を描いていたことは、現在までの10年間の道のりを照らすたったひとつの明かりだったのだな、と話を聞いて感じました。
AIR運営者としてのスキル、マニュアルもないままプログラムがスタートしましたが、実行委員、市民ボランティアが、たった2名だけの事務局スタッフを公私にわたりサポートしてくださり、「アーティストにとってベストなサポートはなにか?」を考えながら、試行錯誤しながら運営を始めたのです。S-AIRのAIRプログラムの最大にして唯一の特徴は「アーティストのやりたいことを出来る限り実現する」という姿勢と支援体制です。「アーティストの本意にそっていけば間違いがない」という柴田の、根拠はないけれど自信に満ちた断言がすべてを表しています。
S-AIRがインターナショナルなプログラム運営者として認知されるに至ったのは、早い時期からインターネットを利用した公募と広報を開始したことが大きな理由です。主に英語でのコミュニケーションとwebを担当して柴田と事務局を担っていた本間貴士が、ITのスキルに長け、というよりもマック(マック=マッキントッシュ/アップル社)おたくだったことが功を奏しました。運営のためのミニマムな人材、ブレインと必要なテクニックを担う人が偶然いた、という奇跡があったからです。
AIR運営者としての大きな野心は最初からなく、まともな給料もなく(笑)、ただ「面白い」に導かれながら10年間の活動を必死で続けてこられたのは、小さな組織を支えた周囲の関係者や環境、札幌の奇跡としかいいようのないことでしょう。

インタークロス・クリエイティブ・センターの外観
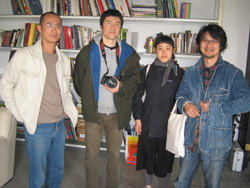
S-AIRのスタッフ
自然のなりゆき──S-AIRプログラムの特徴と変遷
そんな状態でしたから、わたしが運営に参加することとなった2002年に知ったS-AIRは、自分たちが他と違うユニークな運営をしていること、札幌の中でS-AIRという存在にどれだけ発展性があり、可能性を秘めているかということに無頓着で気負いのない組織でした。だからこそ、自由な空気を感じいっしょにAIRプログラムをやってみようと思えたのです。そして、AIRプログラムの存在意義の確立、社会的な認知度をあげていくための新規事業(「アートあけぼの」、「アーティスト・イン・スクール」、「Sapporo II Project」)を立ち上げることができたのも、「試してみたいことは試してみてもいい」という自由な雰囲気があったからです。これがなければ、仕事は続けていられなかったと思います。この環境のおかげで、自分にとって重要な仕事をいくつか始めることができました。
S-AIRのプログラムの特徴は、まず自前のスペースを保有していないことです。制作の場は、若い起業家のオフィスが入居し、のちにプログラム・パートナーとなるインタークロス・クリエイティブ・センターの空きスペースを利用。作品発表やプレゼンテーションの場所は、札幌市内のギャラリーやオルタナスペース、ショップをその都度借りて使っています。自前のスペースを持たないことで、必然的に組織外の団体や人と仕事として繋がっていくしくみになっているといえます。また、その時々の事務局の考え方や、興味、もちろんレジデント(滞在アーティスト)のニーズや、作品の内容意味に合わせて、発表場所をコーディネートできる柔軟性を持つことができました。発足当初、S-AIRのプログラムは、アーティストへの創作環境提供という典型的な欧米型でしたが、国内のAIRに対する事業支援の模索や変化のあおりを受けながら10年の間に変化していきました。このように他の組織、場所との自然発生的な連携を繰り返す中で、次第に札幌という地域に密接したプログラムへと性格を変えていきました。最も、そんなことにも気がつかないまま、日々慌しく仕事をしているうちに自然と変化したともいえるのですが。

滞在アーティスト ユリア・ローマンさん
退屈しないことって必要──地方都市とAIR
発足当時の実行委員やサポーターには、多くの市民や地元で活動する札幌のアーティストが含まれていました。市民、アーティストを問わず、さほど大きいとはいえないコミュニティの中で抱えることになる閉塞感を解消する手段として、札幌という地方都市に、外からのお客さんを喜んで迎えたという印象があります。私自身も北海道出身ではなく、そとからのお客さんでしたし、プログラムで短期間札幌に滞在するレジデントと境遇は同じであったように思います。受け入れ側の札幌にはそんな意味で、ソトからの情報が欲しいという切迫した飢餓感と、観光都市としておのずと身に付いたホスピタリティがあります。そのホスピタリティがいかんなく発揮されるアート・プログラムがAIRであり、AIRは札幌という都市と人の気質との相性が抜群によかったのではないでしょうか。
レジデントからもたらされる、別の視点、作品のプレゼンテーションやコンセプトが地元のアートそのものに影響を与えたかどうか、そのへんは確信がもてません。しかし、言葉の障害は大きいにしろ、レジデントのコミュニケーション・スキル、行動力、移動距離というものがある説得力を持って、地元のアーティストの活動に影響を与えてきたと考えています。すでに札幌をベースに活動をしようと決めたアーティストたちは地元から移動することはあまりありません。そんな中で、地元に残りたいから、または地元で活動を将来に渡り継続してくために、アーティストとして一時的に場所を移動して創作する手段と機会があるのなら、海外のAIRを活利用したいというモチベーションの高まりにはつながっているようです。
この地元アーティストのモチベーションを上げていくという効果があってこそ、地方都市でAIRプログラムが存続する意義ではないかと考えています。こういう活動もあるのか?やってみるかな、たまには気分転換しないと!ということでしょう。
動かないことで醸される文化や思想、発想力というのはあります。ただ、「移動」という行動ものがもたらすダイナミズムやスピード、またブレも時には効果的です。選択がないよりは選択肢のあったほうが、おのずと決断を促し、意思を強く持つことができるのではないかと思っています。
こういった実感をふまえ、札幌市の支援を受けて3年前から地元のアーティストを海外の交流ある機関に派遣するS-AIR AWARDを始め、年間2名を海外に送り出しています。
S-AIR温泉──レジデントの日々とその後
レジデントのほとんどが、S-AIRとは家族のようなつきあいができたと、ありがたい親しみを感じてくれています。レジデントといっしょの小旅行や食事、温泉は、スタッフの趣味を兼ねた楽しみです。AIRプログラムに積極的に参加しようとするそれぞれのアーティストのモチベーションと目的には違いがありますので、一様にすべてのレジデントに対し、S-AIRのこのような姿勢態度がよかったのかどうかはわかりません。ただ、ひとによっては自身の活動場所で個人的な行き詰まり抱え、よその場所へと「逃げて」来るケースがあります。そんなタイプのレジデントとの場合、たまたま滞在した先が「札幌」であったり、「S-AIR」であったりするのですが、彼らの制作に対する瞬発力には凄まじいものがあります。また、何人かのレジデントは、札幌はあまりに刺激がなさすぎて制作に集中するしかなかった、だからいままでとはまったく違う作品ができたし、自分の制作に対する集中力を確認できてよかった、とかのコメントもありました。しかし、いつもと違う場所と人に囲まれ、彼ら自身の「結果」を出すという経験そのものが、アーティストのキャリアにもたらすものの大きさを実感します。アーティストのたくましさと強靭さに驚嘆するばかりです。不思議と、S-AIRでのAIRプログラムを体験して以降、より国際的な活動を可能にし、社会的に成長し評価を受けているレジデントも数は多くいます。なにもないところから作品を生み出すアーティストに、はからずも「なにもなさ」を提供しているS-AIRの功績ではないかとも思えるのです!?
雪は降り続く──冬季の新規プログラム
さらなる面白さを求めて、S-AIRでは冬のプロジェクトに真剣に取り組み始めました。S-AIR周辺では理事や地元のアーティストが「札幌の豪雪を地域資源にできないか」という対話をし、また「なぜ冬や雪でプロジェクトをやらないんだ?」とレジデントやゲスト・アーティストからの提案があり、同時に仕事としてのオファーも起こり、S-AIRの関心は「冬・雪」へと広がっていきつつあります。
大都市でありながら年間約6メートルもの積雪量がある札幌。このあまりに美しい、独特にして最大の特徴を無視するわけにはいきません。雪を地域資源として取り扱うこと、そのような意識をもつ都市になること、新しい意識を構築するためにアートがその活動を先導するために、冬と雪のプロジェクトは、今後、地元のアーティスト、教育機関、ほかの文化施設との連携と恊働していくことはできないか。そうすれば、市民の意識に訴え、都市の活性化につながり、ほんとうの意味でのコミュニティ・プロジェクトへと発展することができるのではないかと期待しています。
そもそも札幌は約半年間が冬季です。そのうちほぼ丸ごと4カ月は雪と共に暮らす日々。いやが応でも、北海道人の気質と精神形成はこの独特の冬を抜きには語れない、と、03年度からの継続事業アーティスト・イン・スクール(07年度以降の企画運営は、AISプランニング:代表 漆崇博)は、冬季実施を重視しています。


アーティスト・イン・スクールのようす
このほかに、08年度までに、S-AIRが企画、あるいはまたは主催として関わってきた2つの冬のプロジェクトがあります。
ひとつは、市内にあるイサム・ノグチが設計したモエレ沼公園を会場とし、すでに5年目に突入した展覧会型の「スノースケープモエレ」(同実行委員会、柴田が企画)。冬季のモエレ沼公園の雪の新しい景色を紹介するイベントとして注目されています。

スノースケープモエレ
もうひとつがスノースケープモエレで発表されたコンセプトを別事業にしたアーティストによるもうひとつの雪まつり「Sapporo II Project」(筆者は発起人のひとり)です。雪を使ってどんな作品をつくるか、という一過性のイベント型、雪まつり型のプロジェクトではなく、プロセス重視、「そこに雪があるからなにかつくろう」という創作態度を促進させるのがこのプロジェクトの目的です。雪とつきあう、というよりは雪からは逃れられない札幌という大都市の日常、有り様に寄り添って活動を進めています。ですから、札幌の日常=除雪活動との連動し、特別な場所ではなく、人の記憶の近く、生活の場でことを起こすことをプロジェクトが自律するまでの環境整備として取り組みます。そこには滞在型現地制作のAIRプログラムは必須となるわけです。今後、さらに機動力を上げるために運営組織を別につくり、教育機関と先生たちの研究グループ、行政の除雪セクション、博物館活動センターなどの公共施設、町内会主催の地域の雪まつりや雪のイベントなどと活動を行ないます。

もうひとつの雪まつり
そして09年度からは、これら既存の冬季事業の連携を試みます。それぞれのプログラムの個性を維持しながら共同で、新しい多面的な冬季プロジェクトを創り出そうと動き始めました。
次の10年──次の世代の人材育成と引き継ぎ
AIRプログラムに参加するレジデントの支援だけにだけに留まらず、AIRプログラム運営そのものが、地元で活動するアーティストにも「マネージメント」というスキルと視点をトレーニングする機会を与え提供することができます。なぜなら、札幌にはマネージメントの人材が未だ少なく、アーティスト自らが自律的に活動の場を作っていくしかない状況です。
厳しい意見に思えるかもしれませんが、これまで数々のアート・プロジェクトに関わってきた経験からあえてわたし個人の見解を述べると、よくも悪くもアーティストの視点は、自分を起点とした一方向の偏ったものに陥りやすいのではないでしょうか。うまく作用すればいいプロジェクトになり、枯渇することのない創造性へと繋がる。けれども、一歩間違えれば独りよがりで、広い支持と共感を得ることの難しい存在になり、社会のはじに追い込まれ自滅していくことにもなりかねません。
回避する方法のひとつに、自分の感性でしか実感を持てないというアーティスト視点ではなく、複数の視点で立体的に物事を検討することのできるマネージメントの視点を備えること、が必要となるのではないでしょうか。
札幌ではこれまでも過去に、アーティストたちが共同で大きな展覧会を行なうアーティスト主体の事業運営活動は存在していました。しかし、アーティスト同士のグループ展という競争原理と切り離せないイベントでは、マネージメントのトレーニングにはなりません。自分のことを脇によけ、他者のために知恵とエネルギーを使う「仕事(ビジネス)」であらなければ、ただの「友情」か「協力」でしかないのです。それらは逆に質を高めていくときの「厳しさ」を回避させ、障害になることも往々にしておきるからです。
事務局には次世代のスタッフを迎え、運営を一新しています。地元の若いアーティストたちが、レジデントという他者のために苦心する仕事を、時間がかかっても地道に手抜きをせず丁寧にやることができれば、客観的な視点を身につけることができるのではないかと思います。多岐にわたるAIRマネージメント業務の種類や内容は、スタッフの経験値を上げ、スキルを身につけるための現場として最適だと思います。
S-AIRもアーティストを中心としたアート仲間、関係者が自主的に始めた組織です。
時代の流れを受けて組織化されましたが、10年が経過すれば、新しかったものにも歴史が生まれます。数カ月の出入りを繰り返すレジデントと同じように、事務局スタッフもたびたび入れ替えを行ないながら、組織としてプライベートの色を持つことを避け、風通しのよい、でも、今まで通り個性的な公共の運営組織に育っていくことを願っています。
わたし自身への反省を含めてですが、相変わらず社会におけるアートに対する認知度は低いままであるように思われます。しかし時間が流れ、世代が移り変わろうとしているいますべての前提は輪郭を和らげています。アートが声高に「なんでもあり」と傍若無人に言い放ってきたつけが回ってきたということでもあるでしょうし、功を奏したということでもあります。社会に対してコミュニケーションを求めながら、実は拒否してきたことのツケかもしれません。社会に甘えることを選んでしまったアートや活動は、社会が頼れる大人ではないという現実にさらされたとき、淘汰されていくのではないでしょうか。
行政がお膳立てしたのではなく、AIRを始めて見ようという自然な空気が、札幌で同時期に活動していた複数のアートの仲間を動かしてS-AIRが誕生した奇跡から10年。この間にS-AIRが社会から頂いてきた支援を、お返しする番。責任ある大人の組織になってしまった。11年目からのS-AIRの課題は、いい意味でのゆるさを保持しながら、今後、行政、地域コミュニティと本気で連携できるかどうか、です。
厳しい課題は自分自身の活動にも跳ね返ります、これからの10年が勝負だと。
さて、ふんどしを締め直さなければなりませんね、笑!
小田井真美
S-AIRの事務局として、アーティスト・イン・スクールなどを担当。現在、世界のアーティスト・イン・レジデンスの情報提供を行なっているオランダのTransArtistsにて研修中。
[2009年6月1日]
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕
2023.5.3レポート:ハイブリッドシンポジウム AIR on air 2.0
2023.2.27AIRと私 09:MAWA(Mentoring Artists for Women Art)滞在レポート