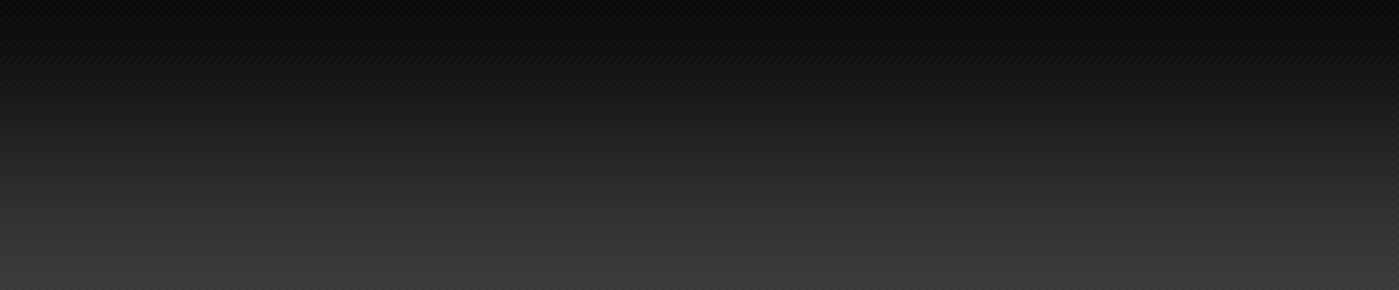

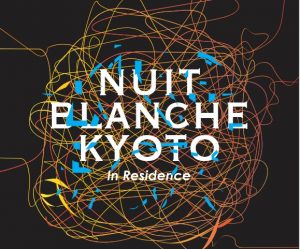
ニュイブランシュKYOTO2025 in Residenceにあわせ、今年のテーマであるアーティスト・イン・レジデンスに関する報告会とトークを行います。アーティスト・イン・レジデンスにご興味のある皆さま、ぜひお越しください。
日時:2025年9月28日(日)
第1部(13:30~14:45):KACレジデンス報告会
第2部(15:00~17:00):クリエーターのキャリアにおける、国際的なアーティスト・イン・レジデンスの果たす役割とは?
場所:京都芸術センター大広間(西館2階)
参加費無料、予約不要
①「KACレジデンス派遣報告会」(2025年9月28日(日) 13:30-14:45)
報告者:臼井仁美(アーティスト)、黒川岳(アーティスト)
進行:西田祥子(京都芸術センター)
京都芸術センターでは、ノルウェーに拠点をおくOCA (Office for Contemporary Art Norway)とのエクスチェンジプログラムを実施しています。ノルウェーからのアーティストの受入のほか、2024年度からは、ノルウェー・ダーレ市にあるAIR施設であるNDK(Nordic Artists’ Centre Dale)への派遣事業も実施しています。今回の報告会では、NDK(Nordic Artists’ Centre Dale)に滞在経験した2名のアーティスト黒川岳氏、臼井仁美氏を招き、それぞれから滞在報告を行っていただきます。※日本語のみ
登壇者略歴
臼井仁美(うすい ひとみ)
東京都出身。海洋生物資源科学を専攻した大学を卒業後、2004年東京藝術大学入学、2010年同大学大学院修了。主な個展に2022年「やまは蔵、まちの原木、ケズリカケの木々」秋田市文化創造館があり、2017年HIAP–Helsinki International Artist Programme、2025年Nordic Artists’Centre in Daleにて滞在制作。先史に木器時代があったことの想像を起点に、人間の自然への眼差しや民俗文化に関心を向ける。作ることが他者と非人間の理解の方法であり、人間の営みと生物の姿、関係性を表す作品を制作する。

黒川岳(くろかわ がく)
1994年島根県生まれ。2016年東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業、2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。自身が出会った様々なものの音や形、動きを注視し、それらを自らの身体で捉えようとする行為を繰り返す中で生まれる形や音、動きなどをパフォーマンスや立体、映像、プロジェクトなど様々な形式で発表している。過去の主な個展に「el cielo y el desierto están haciendo empanadas」(FINCH ARTS、2023年)「甕々の声」(アートラボあいち、2021年)、グループ展に「バグスクール:野性の都市」(BUG、2024年)、「美しいHUG!」(八戸市美術館、2023年)などがある。
②「クリエーターのキャリアにおける、国際的なアーティスト・イン・レジデンスの果たす役割とは?」
(2025年9月28日(日) 15:00-17:00)
登壇者:アデル・フレモル(ヴィラ九条山館長)
石井潤一郎(アーティスト、KIKA contemporary art space)
クリコー・クーシアン(アーティスト、2021年ヴィラ九条山レジデント)
山本麻友美(京都芸術センター副館長)
モデレーター:杉田真理子(Bridge Studio, *** in Residence Kyotoディレクター)
京都は芸術交流にとって理想的な舞台です。フランスはこの文化的首都において、ヴィラ九条山を通じて世界的にも最も名高いプログラムの一つを有しており、一方で京都市はでは、25年前から開始された京都芸術センターのアーティスト・イン・レジデンスプログラムや、新しくスタートした*** in Residence Kyotoのプログラムを通じて、その豊かな創造性を世界のアーティストに開いています。
こうした国際的なアーティスト・イン・レジデンスは、単なる滞在制作の場を超え、アーティストやクリエイターのキャリア形成において重要な転機となり得ます。異なる文化や社会に身を置くことで、新しい表現方法やテーマを獲得し、国際的なネットワークを広げ、次なる活動の可能性を切り拓くのです。本トークでは、実際にレジデンスを経験したアーティストや関係者の視点を交えながら、その意義や課題、そして今後の展望について語ります。
※日仏逐次通訳