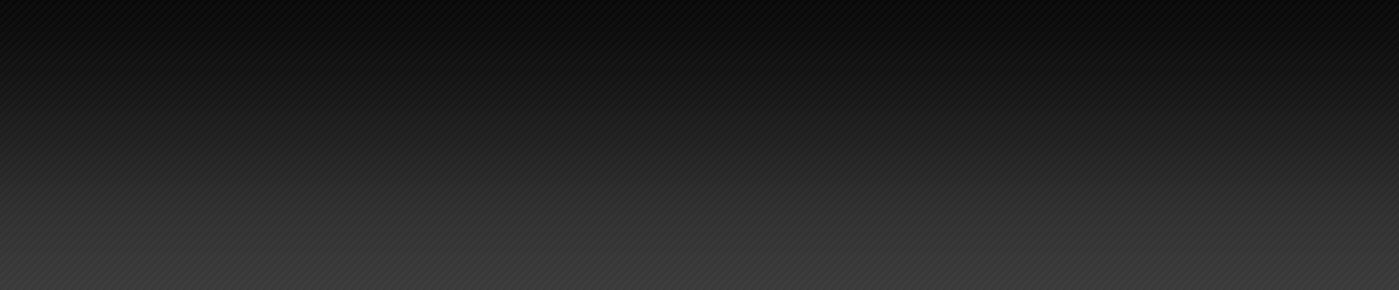

津田道子(美術作家/博士[映像メディア学])
これまでに経験してきたアーティスト・イン・レジデンス(以下AIR)を振り返ることがある。
アーティストは部外者としての保証があってその土地を訪れる、エイリアンみたいなものである。
さまざまな土地を経験して、土地にまつわる気づきや驚きのセンサーが体の中に培われていると感じることがある。そのセンサーを働かせて、滞在する地域にあるものとそれらの関係や歴史に言及して展開する作品は、制作活動自体が成果のひとつといえる。直接それらに言及しなくても、その土地で制作を展開することは、必ずなんらかの関係を築く。
アーティストは地域にある豊かさを掘り起こし、光をあてる存在なのか。
それなら、アーティストがさまざまな土地を経験することを、貢献といえるのではないか。
このレヴューでは、今回のレズ・アルティス総会を振り返り抽出したタームからAIRによる経験の性質の違いを見つめ、「なぜレジデンスするのか?」という問いを自身の経験から検証してみる。
AIR自体に目的がある/ない
10月27日の今総会「セッション9:アーティストの理想のレジデンス」★1で、韓国出身のヨンヘ・チャンと米国出身のマーク・ヴォージュによるアート・ユニット「チャン・ヨンヘ重工業」が発した「なぜレジデンスするのか?」という率直な問いが、セッションをより緊張感のあるアーティスト・トークにした。それに加えて、会場からの「レジデンスはアーティストへのサポートになっているのか?」という質問は「アーティストとはなにか」「アートとはなにか」という根源的な議論を呼んだ。「AIRの意義はアーティストが新しい土地を知り、豊かな時間を過ごすことが根底にある」という彼らの発言に、それぞれの作家も思い当たる節があるようだった。
プロジェクトベースで活動するタイ人アーティストのウィット・ピムカンチャナポンは、アーティストとしての活動が軌道に乗ると、AIRをするチャンスは必然的に発生してくるものだと語った。そのうえで、「アーティストだけでなく家族へのサポートと健全な環境」が理想だと示したことに、どのアーティストも賛成していた。
AIRと呼ばれるものはさまざまなかたちをとっているが、そのなかに滞在制作自体を目的としているものと、美術館や国際展などで展示する作品制作のための長期滞在を指すものがある。
ピムカンチャナポンは、横浜トリエンナーレ2005での共同制作プロジェクトに端を発して、黄金町バザール2008、黄金町バザール2010★2、トーキョーワンダーサイト(2012)へと続いた自身の日本での経験を振り返り、結果的に何度も日本でレジデンスしているが、あくまで展示のためであり、自分はAIRを軸に活動してきた訳ではないと語る。同日の「セッション10:美術館、ビエンナーレとアーティスト・イン・レジデンス」★3でも、大規模な国際展やビエンナーレのディレクターの視点から、「AIR自体が目的ではなく」プロジェクト型の制作をサポートするツールとして、AIRを実施している例が多く紹介された。これはピムカンチャナポンの活動の軌跡と重なる。
同セクションではそれとは少し違う考察が、建畠晢によって語られた。近代都市としての名古屋における「パサージュ」★4を切り口に、「あいちトリエンナーレ2010」を振り返り、国際展は経済的には役に立たないことが多いが、「一過性のイベントとして継続的に残っていくお祭り」であり、それが「文化的な多様性に触れた喜びの記憶として残る」という。AIRも同様に、国際的な展覧会を目的としていない場合でも「文化的な多様性を保証する」と、展覧会の実現のために留まらない、AIR自体の独立した意義についても述べていた。
先述の「セッション9:アーティストの理想のレジデンス」には、日本人アーティストの小沢剛による、二つのAIRのかたちの提案もあった。ひとつは、アフリカ・ウガンダにあるピグミー族の村へ赴いた自身の体験を例に語られた。アーティストが奥地に赴いて、表現のスキルを通して現地の人と関わるというかたちのAIRである。もうひとつは、アートユニット「西京人」★5のミーティング・ポイントとして実施した「セルフ・レジデンス」が紹介された。既存の施設に滞在するのではなく、その都度、状況に応じて滞在場所や制作場所を用意する、施設を必要としないAIRの提案だった。
アーティストが美術館、国際展で作品を発表をしていくなかで、結果的にAIRをし、仕事が成立することは、キャリア形成のひとつのかたちである。そもそもの目的をはたしながら、アーティストは貪欲に気づき、つながりをつくり、AIR自体からも目的を掘り当てているのだろう。アーティスト、キュレーターたちの話の向こう側に、そんなことが見えた。
アーティストの成長──「ボトムアップ」と「トップダウン」
AIRという仕組みは芸術の教育とあわせて見たとき、ここまでとは別のかたちで親和するのではないか。この関心とともにこの日最後の「セッション13:レジデンスを通した新しい創造教育」★6へ向かった。
教育機関とAIRというと、大学にアーティストを招へいして、授業の一環として学生との交流を図るという活動をまず思い浮かべる。しかし、ライクスアカデミー元校長のヤンウィレム・スローファーの話は、20〜30年におよび芸術の教育とAIRを観察することで得られた、学生/アーティストが成長するための仕組みに対する洞察だった。
スローファーはまず、個人の成長の条件として「孤独であること」「対等な同僚との対話」「エキスパートによるフィードバック」など「個人の共同体──Individual Communal」を挙げた。そのあと、AIRを根本的に、二つに分けていた。なにをどのようにするのか、理由も含めてアーティストが決め、帰納的なプロセスをとる「ボトムアップ」型と、それらをマネージャー側やプログラムが決め、演繹的なプロセスをとる「トップダウン」型である。芸術の教育は、プロのアーティストの実践へどう橋渡しするかが第一の使命である他方、AIRはプロのアーティストの実践の一部であるという。アーティストの実践とは作品をつくることだけでなく、作品を通してなににどういう貢献をしているのか自覚を持つことを含んでいる。それは立ち位置を自覚して、「アートとはなにか」「作品とはなにか」という問いへ答えることにつながる。その教育は、標準化されて行なわれるのではなく、学生にも指導者にもアーティストとしての視点があって成立するものだろう。橋渡しをした先を知らないと、橋渡しが成立しないという、単純に考えるだけでは理解できない構造になっている。
スローファーは続けて、学生が若くて人数も多い学部、また修士でも、標準化された教育プログラムでは、成長の条件である「フィードバック」や「対話」は、少し違う秩序を持ってしまい、AIRのほうがそれは重要視されていると述べた。芸術実践に基づく博士課程★7を考えてみると、学生はより少数で必然的に年齢も高いため、実践の経験を積んだアーティストが大学に戻り、創造のプロセスを再認識、再構築する場とすることもある。AIRの機能と対応付けて見てみると、教育の課程が進むにしたがって、トップダウンよりもボトムアップが強くなっていく図式が見え、AIRが教育機関でカバーできないものを補う関係になるのではないかという示唆があった。
教育機関の博士課程に所属しながらAIRもしていた自身を振り返ると、教育機関に「戻った」わけではないが、修了までにどのくらいの期間をかけるのか、どこでどういう形態で作品を発表するのかということも学生である自分自身が決めた。そのプロセスには、実際に多くのフィードバックと有機的な対話があり、すでにある教育プログラムが、学生/アーティストの作品や活動の特質をより引き出すような関係であった。まさに、教育機関の目的をAIRの目的と置き換えることが可能で、実践に基づく博士課程は「ボトムアップ」なAIRととらえられる。
再び、なぜレジデンスするのか
最後に「なぜレジデンスするのか?」という問いに戻る。
総会をとおして自身のプロジェクトをいくつか思い起こした。以降は、自分自身の経験をとおして総会の議論を考察してみたい。
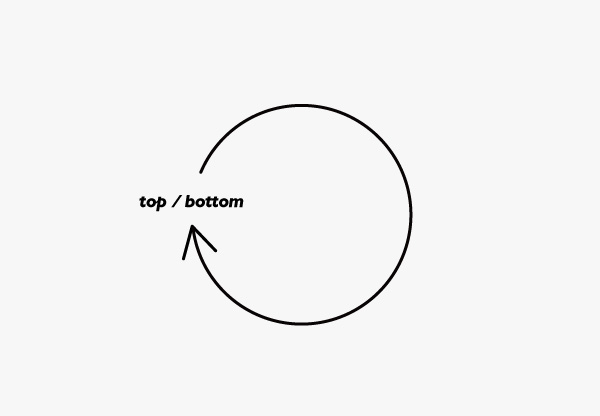
「セルフ・レジデンス」の「トップダウン」と「ボトムアップ」が重なるモデル
まず、フランス人アーティストとの共同プロジェクト「ミグラトリー・プロジェクト」★8を思い出した。フランスと日本とのあいだの距離や時差だけでなく、言葉を含む文化的差異から抜け落ちるものがある。それを埋めるために発生する「移動」ということにメディアを通してアプローチしている。展覧会の機会を理由に、ミーティング・ポイントとしての現地に赴き、状況にあった滞在を用意しながら、プロジェクトを進める。これは、小沢剛の提案にあった「セルフ・レジデンス」と近いかたちを採っていることに気づいた。キュレーターとのやり取りがあったとしても、マネジメントするのはアーティストである自分たち自身である。この「セルフ」型は、スローファーが提示したタームを使うと、ボトムとトップが同じになって、「ボトムアップ」型と「トップダウン」型、両方が一緒にあると言えそうだ。
このプロジェクトでAIRをしているという自覚はこれまで持っていなかったが、根底に流れる「移動」というテーマ自体が目的にもなっているAIRと言える。
海外でのAIRはほかに、インドネシアのジョグジャカルタとバンドゥン★9、韓国の釜山★10といういずれもアジアの地方都市だった。
ジョグジャカルタには2011年の8月に滞在した。当初は2010年12月の予定だったが、出発予定の直前に現地のムラピ山が噴火し、滞在先であるHONF★11のスタッフの多くが被災地へボランティアに行ったため、急遽中止した。そのため、翌年にあらためて滞在することになったのである。はじめは、映像のワークショップをする予定だったが、東日本大震災を経て、ジョグジャカルタへの関心はかたちを変えた。以前から関心があった神話を扱うことへの後押しもあり、噴火があったムラピ山での神話のリサーチを始めた。それまでの表現のスキルから離れたことだったが、そのときそこで取り組むことは自然なことであった。
新しい作品をつくるとき、そのとおりにいくかどうかは別として、着地点を見据える。しかし、このときは着地点を確信しないままジャンプして、まだ着地をしていない。運営側は実験の過程のさまざまな局面で地域へのドアとして働いていた。企画内容が完全に作家に任せられていたという意味で、この経験は「ボトムアップ」型と言えるだろう。

HONF(ジョグジャカルタ、2011年8月)

ムラピ山(ジョグジャカルタ、2011年8月)
これまで、AIRの目的とAIRの主導者という観点から個人的な経験を振り返った。すべての場合を網羅していないが、自分自身の作家活動を通して、「なぜレジデンスするのか?」ということを考えるためである。AIRの期間中、制作活動や生活などを通して、アーティスト同士、もしくはアーティストと地域の人の「いま・ここ」の経験が分けられないものになる。そのなかで気づきを繰り返し、制作を続けていることは、文化的多様性に貢献することであり、世界へ還元されるだろう。AIRの目的、決定権の所在、組織体制が地域の人や他のアーティストとのつながり方をかたちづくり、結果的にそのAIRで「経験すること」のかたちをもつくっていることが見えてきた。
★1──レズ・アルティス総会2012東京大会「セッション9:アーティストの理想のレジデンス」(東京ウィメンズプラザ、2012年10月27日、14:00-15:00)。登壇者=田中功起(アーティスト/日本)、小沢剛(アーティスト/日本)、チャン・ヨンへ重工業(アーティスト/韓国、アメリカ)、ウィット・ピムカンチャナポン(アーティスト/タイ)、モデレーター:家村佳代子(トーキョーワンダーサイト プログラム・ディレクター)。URL=http://www.resartis2012tokyo.com/
日本人アーティストの田中功起は、7人のピアニストがピアノを弾くといった、共同制作を扱った新作を紹介し、パリのパレ・ド・トーキョーでのレジデンス(2005-2006)のなかでの共同制作の経験が、アイディアのもとになったと語った。他の滞在型制作も踏まえて、理想のレジデンスの条件を五つ──義務がないこと、潤沢な予算、継続または終わらないこと、地元のアートシーンとのつながり、あらゆる意味でのサポート(No obligation, Enough production budget, Several times or never ending, Connection between local art scene, Supportive)──挙げ、個人的なつながりが生まれることがもっとも大事であると述べた。
★2──2010年は建築家の遠藤治郎との共同制作。
★3──同東京大会「セッション10:美術館、ビエンナーレとアーティスト・イン・レジデンス」(東京ウィメンズプラザ、2012年10月27日、15:30-16:30)。登壇者=デヴィッド・エリオット(2012年キエフ・インターナショナル・コンテンポラリー・アート・ビエンナーレ(ウクライナ)アート・ディレクター、森美術館初代館長/ドイツ)、建畠晢(京都市立芸術大学学長、埼玉県立近代美術館館長)、キム・ホンヒ(ソウル市立美術館館長/韓国)、ワシフ・コルトゥン(SALT Research & Programs ディレクター/トルコ)、モデレーター:今村有策(トーキョーワンダーサイト館長、東京都参与)。
★4──ヴァルター・ベンヤミンの草稿群をまとめた『パサージュ論』には19世紀から20世紀のパリの街の変遷についての考察がなされている。建畠は、近代都市へと整えられた名古屋において、長者町を残された現実のパサージュととらえ、都市の欲望を反映する地域でアートを展開することを「あいちトリエンナーレ2010」の意図としていたと述べた。
★5──小沢剛と中国人アーティスト陳劭雄(チェン・シャオション)と、韓国人アーティスト、キム・ホンソク3人から成るユニット。
★6──同東京大会「セッション13:レジデンスを通した新しい創造教育」(東京ウィメンズプラザ、2012年10月27日、17:00-18:00)。登壇者=アラヤー・ラートチャルムンスック(チェンマイ大学准教授/タイ)、クリス・ウェンライト(キャンバーウェル、チェルシー、ウィンブルドンカレッジ、ロンドン国立芸術大学の統括学長/イギリス)、ヤンウィレム・スフローファー(ライクスアカデミー元校長/オランダ)、藤幡正樹(東京藝術大学芸術情報センター長/日本)、マックス・デラニー(モナッシュ大学美術館長/オーストラリア)、モデレーター:家村佳代子(トーキョーワンダーサイト プログラム・ディレクター)。
イギリスのロンドン国立芸術大学や、学内にレジデンス・スタジオがあるというオーストラリアのモナッシュ大学は、おもにアーティストを招へいして、授業の一環として学生との交流を図るという活動を紹介した。それと違い、藤幡正樹によって紹介された東京藝術大学の「DOUBLE VISION」(2010年に開催された、トーキョーワンダーサイト、フランス・ナント芸術大学、東京芸術大学と武蔵野美術大学による共同プロジェクト)は、学生自身が学内活動の一環としてナントと東京で相互に短期滞在と制作をするというプロジェクトであった。同大学の藤幡は、日本において、文化予算と比べて教育のほうがまだ少し余裕があり、美術教育は「ならいごと」や「教養」を担うのではなく、「活動」としてのアートの場をつくり、どうリアクションを起こすかを見る場所だと語った。
★7──『芸術実践領域(実技系)博士プログラム資料』(東京芸術大学芸術リサーチセンター、2012年11月3日)のなかから『芸大博士プログラムに関する所見』(ジェームス・エルキンス)によれば、現在、国際的に急速にその数が増えている。
★8──キャロライン・バーナードとダミアン・ギシャールと3人による共同プロジェクト。2007年からフランス、スイス、日本という離れた土地に居ながら、おもにインターネット経由での対話をとおして制作を続けている。
★9──いずれも国際交流基金からの助成を受けた。
★10──Space Bandeeという釜山のNPOが開催するオルタナティブ・スペースだったが、2011年11月に拠点としていた建物は取り壊され、現在は活動を休止している。
★11──「The House of Natural Fiber | yogyakarta new media art laboratory」の略称。new mediaのフェスティバルやレジデンスを実施している。ディレクターはトミー・スリョ、ヴィンセンシウス・“ヴェンザ”・クリスティアワン、イラン・アグリヴァン。ヴェンザは2002年に茨城県守谷市のアーカス・スタジオにも滞在しているアーティスト。
インドネシアで、教育機関や美術館などの文化施設のインフラが限られているなか、自宅を改装してイベントを興し、海外からのアーティストを受け入れているHONFのメンバーを尊敬する。アーティストとしてヨーロッパや他のアジアの国などで発表しながら、海外からのアーティストをAIRで招き、強いつながりをつくることが芸術文化の底上げとなり、それが彼ら自身のためになると、明確な目的を持っている。一方で、その資金の多くはオランダに頼っていることも忘れてはいけない。ヨーロッパ、アメリカ、アジア諸国とも違う芸術文化の掘り起こしがどうなるのか、興味深い。
つだ・みちこ
1980年生まれ。美術作家。東京芸術大学大学院映像研究科後期博士課程修了、博士(映像メディア学)。個展=「Travelling」(CHUV、ローザンヌ、2012)、「配置の森の住人と王様」(NTT ICC、東京、2012)。国際芸術センター青森、秋吉台国際芸術村など国内外でレジデンスもしていた。http://2da.jp
[2013年4月]
関連論考:AIR_J>Article>
レズ・アルティス総会2012東京大会レビュー[1]鷲田めるろ「マイクロ・レジデンスの可能性」
レズ・アルティス総会2012東京大会レビュー[2]光岡寿郎「社会的流動性の指標としてのAIR」
2023.7.5京都市内の滞在制作型文化芸術活動に関するアンケート調査〔報告〕
2023.5.3レポート:ハイブリッドシンポジウム AIR on air 2.0
2023.2.27AIRと私 09:MAWA(Mentoring Artists for Women Art)滞在レポート